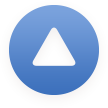<江戸末期>
●科学機器の源流
15~16世紀ごろの西欧において、人類に科学的な考え方が芽生え、近代科学が登場した。その研究道具として、近代科学とともに発展していったのが科学機器である。現在の科学機器は、フラスコ、ビーカー、試験管等の器具類に始まり、理化学機器、分析機器、計測機器、試験機器、実験室設備にいたるまで、実に多岐にわたっている。日本における科学機器は、幕末から明治にかけて、つまり明治維新のころに近代科学が導入されたことから、その歴史が始まった。欧米ではすでに近代科学が爛熟期にあった頃である。
しかしながら、それ以前より我が国には科学機器の源流はあった。そもそも科学機器は、古くより人々の生活と密着して生まれた既存の道具や技術の応用によって作り出された。例えば、度量衡器、測量器、医療器具などの道具、硝子細工、彫金、鋳造、鍛造等の技術である。日本でも江戸時代には、そうした道具や技術が測量学や天文学、医学、蘭学などの分野で活かされていた。
中でも測量学の発達は注目すべきだろう。伊能忠敬が1800(寛政12)年から1816(文化13)年にわたり全国を測量し日本で最初の近代的地図『大日本沿海輿地全図』を作成したのは有名な史実である(完成は1821〈文政4〉年)。伊能忠敬は、測量術側尺、間縄、観星鏡、象限儀(天測に使用)、方位盤、杖先羅針盤、垂揺球儀、振子時計、測食定分儀、子午線儀、望遠鏡、磁石、コンパス、量程車(車の回転数によって距離を測るもの)などの器具を使用していたという。
蘭学による影響も大きい。1774(安永3)年、前野良沢、杉田玄白らの『解体新書』が刊行されるなど、蘭学が盛んになり始めた18世紀後半では、蘭学者によって実験や研究が行われるようになった。本草学者であり作家、陶芸家、画家、発明家として知られる平賀源内も若いころより蘭学を学んだ。そして、源内自らが1750年代より近代科学の先駆けともいうべき器具を創り出していった。例えば、量程器(現在の万歩計)、磁針器(方角を測る道具)、火浣布(燃えない布)を創出した。また、オランダ製の寒暖計をみただけで原理を理解し、タルモメイトル(寒熱昇降器)を作成した。これが我が国で初めて作られた寒暖計だといわれている。1776(安永5)年には、日本初の発電器エレキテル(摩擦静電気発生装置)を完成させた。
1837(天保8)年には、蘭学者宇田川榕菴(ようあん)による化学書『舎密開宗』が刊行され、日本に化学という学問が初めて紹介された。宇田川榕菴は、他の書『開物全書名物考」』で蓄電池、気体発生装置、気体捕集器などの化学実験装置について述べている。ちなみに、この頃はまだ化学という言葉はなく、1860(万延元)年に川本幸民が翻訳したオランダ化学書『化学新書』において、「化学」という日本語が初めて現れたといわれている。
同じく蘭学を学んだ佐久間象山は、1847(弘化4)年、ガラス原料に硼砂を取り入れることにより、硬質ガラスの製造を始めた。どのようなガラス製品を作ったのかは定かではないが、硬質ガラスの製造技術は、耐熱、耐水、耐薬品性を要する医学用・理化学用ガラスの製造に欠かせないものであった。そして、医学用・理化学用ガラスは近代科学における実験器具の原点であり、科学機器の初期の段階から存在する器具でもある。そう考えると、佐久間象山は、日本における医学用・理化学用ガラス製造の始祖であり、のちの日本の理化学機器の発展に多大な貢献をしたといえるかも知れない。なお、のちに佐久間象山はこの技術を、江戸切子を作り出した加賀屋久兵衛に伝えたといわれている。
加賀屋久兵衛が営んでいた加賀屋が、江戸時代に発行した引札(一枚刷りの商品カタログ)には、化学用ガラスとして、すでにランビキ(レトルト)、バルモメートル(晴雨昇降バロメーター)、ホクトメートル(比重計)、テルモメートル(寒暖計)などが掲載されている。中でも、テルモメートル、ホクトメートルは、蘭学者であり医学者でもある杉田玄白、大槻玄沢らが上記の製造に関する知識を授けたといわれている。また、レトルトは蘭学者・川本幸民の門人から依頼を受けて製作したといわれており、蘭学とガラス製造が密接に結びついていたことを伺い知ることができる。
このように、江戸末期に医学用・理化学用ガラスの製造の芽が出始めたとはいえ、実験器具類は従来の陶器などを代用することもあったようだが、ほとんどは輸入製品であった。江戸幕府直轄の洋学研究教育機関である開成所(1855〈安政2〉年に発足、当初は洋学所、そののち蕃書調所)では、精錬学のもと実験、薬品の製造、分析などが行われていたが、その実験道具はオランダから輸入していたという記録が残っている。
<明治時代>
●輸入事業の始まりと国産化の胎動
1867(慶応3)年、明治天皇が即位し、江戸幕府による大政奉還を受け、王政復古によって明治新政府が発足した。いわゆる明治維新である。1868(明治元)年に時代は江戸時代から明治時代に移ることになる。
明治新政府により、欧米から多くの学者や技術者が招聘され、近代科学の研究や教育が始められた。例えば、明治政府が開成所を引き継ぐかたちで開校した開成学校は、1873(明治6)年、専門学校に転換し、従来の「語学課程」(普通科)に加えて「専門学課程」(専門科)として、法学・工学・化学・鉱山学・諸芸学が新設された。これより、理化学教育の土台が築かれた。なお、開成学校は後に一部が東京開成学校本科となり、1877(明治10)年、東京医学校と統合されて東京大学となった。
当時はまだ江戸時代と同じく、研究に必要な実験用諸器具などは外国人教師が持参するか、本国より取り寄せていた。また、日本人の研究者が共同で実験用諸器具を海外から購入することもあった。そうした日本人研究者のうち内務省衛生試験所初代所長であった村橋次郎氏が、宇都宮三郎氏、保田東潜氏、大鳥圭介氏らの協力を得て、1878(明治11)年に輸入商社「離合社」を銀座に設立した。離合社という名は、当時物理化学の呼称「離合学」にちなんだものである。これにより、日本において事業としての科学機器の輸入が始まったのである。
科学機器の本格的な輸入が開始される一方で、前述したように、日本における伝統的な職人技術が土台となり、科学機器の国産化も動き出していた。1874(明治7)年、開成学校内に製作学教場が創設され、学校で使用する理化学器械の修繕や製造が開始された。
1875(明治8)年には、島津源蔵氏が島津製作所を創業し、教育用理化学機器の製造を始めた。そもそも島津源蔵氏の本業は仏具製造であったが、近くにある京都舎密局に足繁く通い、理化学の講座を受講していた。京都舎密局は、明治政府の殖産興業政策のもと、理化学の授業と実業の指導を行う、いわば技術導入の拠点であった。そこで島津源蔵氏には、“わが国の進むべき道は科学立国である”という理想が芽生えたという。そしてのちに京都舎密局の教師となったドイツ人技師、ゴットフリード・ワグネル氏からも多くの新しい知識や技術を学んだといわれている。島津製作所から1882(明治15)年に発行された「理化器械目録表」には、理科の授業に使う実験器具として5部門・110種類の製品が掲載されている。
また、前述したように江戸末期より製造が試みられていた化学用ガラスの製造も盛んになっていった。その例として、明治時代に発行された加賀屋の引札に掲載されている化学用ガラスは、江戸時代よりも種類が多くなり、形の違うレトルトが4種類、一球安全漏斗管のような高級な化学用製品が記載されている。なお、1879(明治12)年加賀屋の2代目である皆川久兵衛が発起人となり、東京玻璃製造人組合が創立された(改変を経て、現在の一般社団法人東部硝子工業会となっている)。この組合に加入した硝子製造人は、日本橋を中心に74名に上った。
以上のように、明治初期では、国家の殖産興業政策に主導された官営の勧業・教育機関と深く関係しながら、日本の科学機器の土壌が形成されていったといえよう。
●日本の近代化と内国勧業博覧会
明治時代では近代国家を目指すべく、産業育成(殖産興業)と軍事力強化(富国強兵)が図られた。特に、造船、鉄道、電信・電話、鉱山、鉄・機械・蒸気罐の製作、そして艦船や武器といった軍需品の製造など、重化学工業化が急速に進んでいった。
そんな中、殖産興業推進のために、日本で初めての内国勧業博覧会が1877(明治10)年に開催された。近代技術の展示場ともいうべき博覧会は、すでに欧米諸国で盛んに開催されており、1851年にはロンドンで世界初の万国博覧会が開催されていた。日本も1867年(慶応3年)のパリ万博に参加している。そして明治期に入り、内国博ではあるが、いよいよ日本でも国家的な博覧会が開かれるようになったのである。
この博覧会は、西洋技術の紹介、国内産業の競争・発展を企図するものであった。第1回目では、鉱業及び冶金術、製造物、美術、機械、農業、園芸という6つの部において、全国から出品物が集められた。素材・製法・品質などさまざまな面から審査が行われ、優秀作には賞牌・褒状等が授与された。島津源蔵氏は医療用ブジー(拡張器具・ゾンデ・細管)により褒状を、1881(明治14)年に開催された2回目の同会では、蒸留器が有功2等賞を授かったという。内国勧業博覧会は回を重ねるごとに規模が大きくなり、来場者も増えて盛況を博すようになるが、日露戦争後の財政難を理由に1903(明治36)年の第5回で終焉を迎えた。
●明治後期における科学研究
明治も後期となり、近代国家としての体をなしていくにつれて、日本は国際社会の荒海へと乗り出すようになる。1894(明治27)年には日清戦争(~ 1895〈明治28〉年)が、1904(明治37)年には日露戦争(~ 1905〈明治38〉年)が勃発した。いずれの戦争においても日本は勝利し、国際社会においても列強の仲間入りを果たした。
日本の科学研究の成果が出始めるのもこの頃である。例えば、池田菊苗博士は1907(明治40)年にうま味成分として知られるL-グルタミン酸ナトリウムを発見した。また鈴木梅太郎博士は、当時恐れられていた脚気の治療に玄米食が有効であることに注目し、1910(明治43)年、米ぬか中から有効成分のアベリ酸(のちにオリザニンと改名)の分離に世界で初めて成功した。この成分こそが、現在のビタミンB1で、世界で最初に発見されたビタミンであった。しかしながら、世界的にはビタミンB1の発見において、オランダのクリスティアーン・エイクマンの功績が知られ、フレデリック・ホプキンズ(イギリス)とともにノーベル医学・生理学賞が贈られている。この背景には、当時の日本科学界の体質的な問題を内包していることが示唆されている。
一方、世界ではすでに科学研究機関の整備が進んでいた。1870年代には、ヨーロッパ諸国、アメリカにおいて、国立科学研究所が設立され、1890年代には大企業が独自の科学研究機関を設けるようになった。また、1900年頃から、ロックフェラーやカーネギーなどの財団法人組織の研究機関も設置された。
現在も世界的な賞として知られるノーベル賞が創設されたのもこの頃であり、1901年に初の授賞式が行われた。なお、初のノーベル医学・生理学賞の最終候補者の中には「日本の細菌学の父」として知られ、日本の近代医学の発展に寄与した北里柴三郎がいた。このノーベル賞がその後の科学研究の発展に大きな影響をもたらしたことは周知の事実であろう。そして、20世紀前半には、アインシュタインの相対性理論に象徴される新しい宇宙観・物質観を構築した科学革命を迎えることになる。
●明治後期の科学機器
明治時代において、科学機器は輸入と国産化という2つの流れの中で発展していったが、明治の終わりになっても輸入製品が市場の大半を占めていた。とはいえ、高橋 智子氏の調査によれば、 明治期の科学機器の製造業者は基本的には零細で、 職人的な小規模業者ではあったが、かなりの数に達していたという(「1910-1925年における日本の科学機器産業とその生産技術」東北大学大学院国際文化研究科論集第6号)。
なお、1906(明治39)年に島津製作所が発行したカタログには、自社製品だけではなく、輸入品や国内取次商品も含んだ、2,000点以上の物理機械と約700点の化学機器が掲載されている。このカタログの品目をみると、当時の科学機器の一端を伺い知ることができる。
●東京大正博覧会にみる大正初期の科学機器
大正となってもまだ国産の科学機器は少なく、加えて科学機器を扱う業者の多くは、医療器械が主力の製品であり、科学機器は3割ほどにすぎなかった。そのため、科学機器が独自の業界として形成されるには至っていなかった。当時、教育用の製品を扱う業者の団体として東京教育品同業組合が存在していたが、科学機器を扱う業者の多くは、この組合の第一部会に加入していた。
しかしながら、1914(大正3)年に東京府の主催で開催された東京大正博覧会では、80の出品者(企業・個人も含む)によって、医療機器を除いても1,000点以上の科学機器が出品されていた。受賞作品の中には、顕微鏡などの光学機器類、レントゲン装置、理化学用硝子製品などがみられ、明治期よりも国内製造による理化学機器の種類が増えていることが窺える。
<大正8年、業界団体設立から敗戦まで>
●東京理化学器械同業組合の設立
1914(大正3)年、第一次世界大戦が勃発。大戦によって産業の重化学工業化がさらに進められるとともに、科学機器の需要が高まっていった。しかし、戦争によって欧米からの輸入が途絶え、科学機器が我が国に入らない状態であった。そのため、科学機器の国産化が急速に進められた。結果、多くの専業メーカーが誕生。遠心機などの汎用機器や当時の先端機器であった自動測定機器などが製作されるようになった。第一次世界大戦によって、日本の科学機器業界の形成が促進されることになったのである。
そして、第一次世界大戦の終戦から2カ月後、1919(大正8)年1月に、東京教育品同業組合第一部を分離し、東京理化学器械同業組合が設立された。設立にあたっては、田中杢次郎、山越長七、島津源吉、初代森川惣助、須賀孟伯、山野国吉、川井金三郎、中村勝太郎、松野芳次郎の諸氏が尽力された。初代組合長には、当時、業界のリーダーの一人であった田中商事株式会社(現・田中科学機器製作株式会社)の田中杢次郎氏が就任した。
この組合創立により、日本の科学研究にとって力強い支援組織が確立されたとともに、科学技術の発展に向けて、なくてはならない土台がつくられたといえよう。
●科学技術政策の積極化
大正期、特に第一次世界大戦を境にして、政府は科学技術政策に積極的に乗り出すようになった。例えば、1917(大正6)年に、政府の科学技術研究に対する補助が始まり、1919(大正8)年~ 1926(昭和元)年の間には、33の試験・研究機関が新たに創設されている。中でも、1917年に創設された理化学研究所は、現在も日本で唯一の自然科学の総合研究所として継続している。理化学研究所は国立ではなく財団法人としての設立であったが、政府にて設立発起協議会が開催されるなど国が積極的に関与していた。
民間企業の研究機関もこの時期に増加しており、東芝の前身である東京電気、ミツワ石鹼、三菱造船、芝浦製作所の研究所などが設立されている。1923(大正12)年の調査では163カ所の施設があったとされるが、当時は個人の発明力に依存していたため、零細規模の研究所が多かったようである。
また、1921(大正10)年、改正度量衡法の公布、同年の工業品規格統一調査会の設置、特許法の改正など、法整備も行われた。さらにこの年には、軍需工業の奨励のために、民間事業者を対象に工業研究奨励金の交付も開始されている。
この頃は、このように科学技術政策が推進されるとともに、基礎となる教育も拡充されていく時期でもあった。1918(大正7)年に大学令・高等学校令が公布され、翌年施行されて、多くの官立大学、高等学校、高等専門学校が増設されている。これにより大学数では約10倍、学生数で5倍強、高等学校・高等専門学校では学校数と学生数ともに、約2倍増加した。
このような社会的背景は、科学機器の必要性をますます高めるものであった。
●大学研究室とメーカーとの密接な関係
研究機関、特に大学研究室は科学機器の大きなマーケットでもあったが、一方で、科学機器メーカーにアイデアや機器開発の情報を提供するという役割も担っていた。研究室とメーカーが密接にかかわることによって、研究に必要な機器が開発されていったのである。このような二重性は、その後もずっと継続し、科学機器の発展に大きく寄与することになる。
当時において、その一端を示すエピソードがある。化学工業界の発展に尽力した応用化学者、東京大学名誉教授の田中芳雄先生の話である。
「私が米国へ留学のために出かけた大正4年ごろまでは、研究費もなく、実験器具の設備も乏しく市販品も少なかった。<中略>私が大正7年に米国から帰朝してから、多少の研究費の融通がつくようになったので、私どもの研究は急速に進んだ。そのために、私どもの研究に必要な実験器具や機械をみずから設計し当時の千野製作所、西製作所などと連絡して製作した。
このような方法で、私どもにより初めて製作されたものは、電熱式フラスコ加熱器、たこ足式蒸留受器、恒温槽、ゲーデ式オイルポンプ、マクレオドゲージ、オゾン発生器、油類の自然発火測定器一式、燃焼範囲測定装置、そのほか複雑なガラス器具などであった」(田中芳雄「私の追憶と今の感想」日本分析化学会創立10周年記念誌より)
●「T.R.K」カタログの刊行
東京理化学器械同業組合の設立の翌年、1920(大正9)年3月には、日本を第一次大戦の戦後恐慌が襲った。戦後も好景気が続いていた日本経済であったが、復興したヨーロッパ諸国が市場に復帰したことにより、輸出や国内の需要が減少、輸入超過となり、株価が大暴落したのである。銀行は取り付けや休業、合併が相次ぎ、大戦中に新興した企業や事業を拡大した企業の多くが倒産していった。この戦後恐慌以降、日本は長期にわたり慢性的な不況に陥ることになる。
しかしながら、こうした恐慌と不況の嵐のなか、科学機器業界はその影響をあまり受けることなく、比較的穏やかに発展を続けていった。なぜなら、前述したように科学機器の主な需要先は、官庁や教育機関であったため、安定した収益が得られたからである。
東京理化学器械同業組合は、精力的に諸事業を展開していった。まず着手したのが、専門理化学器械の目録の制作である。当時、科学研究が拡充していったことにより、研究部門から理化学器械の目録の要望が高まっていたのである。そこで、1920(大正9)年、組合長の田中杢次郎氏が自社で出版していた総合カタログ(田中合名会社型録第6版)と月刊誌「化学之友」の版権(銅版刷版)を同業組合に提供した。それをもとに編纂が行われ、1922(大正11)年3月に「T.R.K」カタログ(T.R.K型録)という名で完成、全国3万カ所の需要家に提供された。
掲載されている科学機器は、ビーカー、フラスコなどの硝子器具から振とう攪拌機、ガス分析器など多岐にわたる。中には、当時では貴重な研究機器であったと思われる電気オゾン発生器の掲載もあった。
この「T.R.K」カタログは永らく業界標準とされ、戦後の「N.R.K」に受け継がれることになる。
●平和記念東京博覧会への出展
東京理化学器械同業組合は、業界の社会的認識と産業としての位置づけを図るために、発足当初より、展示会活動を重視してきた。同組合として初の出展は、1922(大正11)年、3月10日から7月31日までの期間、東京・上野公園、不忍池畔にて開催された平和記念東京博覧会であった。この博覧会は、大戦後の不況が続き、また前年の1921(大正10)年11月に、時の総理大臣原敬が刺殺されるなど、不安定な社会情勢のなかに開催された。そうした社会の空気を払拭すべく、同博覧会では自由平和が強調されるとともに、明治期の博覧会のような殖産興業的な色彩は薄れ、文化国家としての日本がアピールされた。
一つのブロックに、組合員より募った出品物を回転式のディスプレーに展示した。放射状に並べられた出品物がゆっくりと回転するディスプレーは、そのアイデアが評価されて、金牌を受賞した。
その後も、昭和初期に開催された文部省主催による上野博物館の展示会や朝鮮の博覧会に出展するなど、活発に展示会活動を展開した。
「T.R.K」カタログの刊行や博覧会への出展など、当時のこうした活動が原型となり、今日の業界活動につながっていくのである。
●関東大震災と「T.R.K」カタログの復刊
景気の回復をみない中、さらなる不幸が日本を襲った。1923(大正12)年9月1日午前11時58分に起こった関東大震災である。関東地方に発生したマグニチュード7.9の激震により、火災、津波、家屋の倒壊が起こり、死者・行方不明10万5千余、全壊焼失家屋約42万戸という甚大な被害をもたらした。
第一次大戦の戦後恐慌以降の不況下にあっても、発展を続けてきた科学機器業界であったが、地震によって大いなる打撃を受けた。東京理化学器械同業組合の組合員の多くが、工場、事業所を焼失した。そのため、同組合では組合員相互の協力を訴え、かつてない困難を乗り切るように努力した。その一つが、震災により原版すべてが焼失した「T.R.K」カタログの再刊である。
震災後の混乱のなか、急遽制作に着手、1925(大正14)年4月に再刊を果たし、ユーザーの期待に応えた。単なる再刊ではなく、第1版の不備を訂正した第2版として刊行された。
●大正から昭和へ 昭和恐慌のなか、東京理化学器械同業組合、創立10周年
1926(大正15)年12月に大正天皇が崩御し、時代は昭和となった。その翌年1927(昭和2)年3月には東京渡辺銀行およびあかぢ貯蓄銀行の休業を皮切りに銀行の取り付け騒動が起きた。関東大震災以降、震災手形の処理をめぐって、金融不安に陥っていた日本は、この取り付け騒動をきっかけに一気に金融恐慌に陥った。世にいう昭和恐慌である。
昭和の時代は社会的不安が漂う中から始まった。
1929(昭和4)年4月14日、東京理化学器械同業組合は創立10周年を迎えた。上野精養軒において記念式典が開催され、組合員180名、来賓20名が集った。
当時の組合長は、山越長七氏、式典委員長は斉藤熊三郎氏が務めた。式典では、10年勤続役員として、山越長七、島津源吉、森川惣助(初代)、須賀孟伯の4氏が表彰された。
●世界恐慌のなか、「T.R.K」カタログ第3版が完成
この式典から半年後、アメリカニューヨーク株式市場において株価が大暴落した。いわゆる暗黒の木曜日である。このことが口火となって、世界恐慌が巻き起こった。日本もこの世界恐慌の波に巻き込まれ、生糸相場の下落など経済は混乱の様相を見せた。不景気が続き、失業者は増えていった。
そんな世にあっても、科学機器業界は政府の科学技術政策およびそれに基づいた学校教育の拡充に支えられ、安定した発展を続けていた。科学技術の進歩とともに科学機器の開発が進み、1925(大正14)年に発刊した「T.R.K」カタログ第2版の大幅な改定が必要となるほどであった。そこで、世界恐慌の只中にありながらも、1930(昭和5)年6月、「T.R.K」カタログ第3版が完成した。
●昭和初期の科学研究
20世紀前半は科学革命といわれ、相対性理論や原子核物理学によって新しい宇宙観・物質観が構築された。日本では1935(昭和10)年に、湯川秀樹博士が中間子の存在を予言したことが象徴的である。ちなみに、後に中間子の存在が証明され、湯川博士は1949(昭和24)年、日本人初のノーベル賞(物理学賞)を受賞した。
また、科学機器と最も関係の深い分野である化学研究では、量子化学、高分子化学の研究が活発に行われ、成果を上げていた。科学技術においても、世界的に革新的な発明が相次いだ時代であった。例えば、電子顕微鏡、ジェット機、液体燃料ロケット、レーダー等が開発された。
日本でも、大学の研究室・工業試験所などの官公立研究機関や理化学研究所が先駆的研究を実施し、数々の成果を上げていた。特に理化学研究所は、第3代所長 大河内正敏氏のもと、主任研究員制度(主任研究員の自由裁量により研究を行うことができる)により、大きな発展を遂げた。この頃の理化学研究所は、鈴木梅太郎(ビタミンB1の発見)、寺田寅彦(物理学者・随筆家・俳人)、長岡半太郎(土星型原子モデルの提唱)、本多光太郎(磁性鉄鋼の開発)、湯川秀樹(中間子論によりノーベル物理学賞受賞)、朝永振一郎(くりこみ理論によりノーベル物理学賞受賞)など、非常に多くの科学者が活躍していた。
また、大河内所長は研究成果を事業化するために理化学興業(株)を1927(昭和2)年に設立し、のちに「理研産業団」(理研コンツェルン)を形成した。最大規模となった1939年頃には、会社数は63、工場数121となるほどであった。
理化学研究所では、研究設備や機械器具、測定器などに多額な資金が投じられるとともに、大河内所長の考えにより外国の研究機器を使用することはなかった。独創的な研究のための器械は所内で製作していた。こうして生まれた新技術は、科学機器業界にも恩恵をもたらし、業界の発展に大きく貢献したのである。
●軍の台頭と戦時体制への移行
日本は昭和に入ると軍国主義が急速に進行していった。1927(昭和2)年から1928(昭和3)年にかけて、3度にわたって行った中国山東省への派兵、いわゆる山東出兵、1928(昭和3)年の関東軍による張作霖の暗殺(満州某重大事件)など、中国における日本軍の動きが活発化した。1931(昭和6)年には満州事変が勃発、翌年には満州国が建国された。満州事変を契機に日本は列国より非難を受ける立場となり、1933(昭和8)年国際連盟を脱退、日本はドイツとともに国際社会から孤立してしまう。そして、1937(昭和12)年の盧溝橋事件(盧溝橋で日中両軍が衝突した)を経て、ついに日中戦争へと発
展するのである。
日本国内においては、1928(昭和3)年の初の普通選挙による総選挙で予想外の進出を果たした無産政党や日本共産党に対する弾圧が強められ、共産党系活動家の大量検挙が行われた(三・一五事件)。その後、国体変革を目的とする結社の指導者に対する最高刑を死刑とするよう治安維持法を改正、これらの出来事を踏まえ、内務省には特別高等警察が設置され、いわゆる“特高の恐怖時代”に突入した。
そして、1932(昭和7)年、大日本帝国海軍の青年将校達が時の内閣総理大臣犬養毅を殺害した五・一五事件、1936(昭和11)年、陸軍皇道派の影響を受けた青年将校らが起こしたクーデター未遂事件である二・二六事件が起きるなど、軍ファシズムの動きが高まっていった。
●経済統制における東京理化学器械同業組合の動き
日中戦争の激化に伴い経済の戦時体制化が必要となり、1938(昭和13)年に国家総動員法が施行され、太平洋戦争の終結をみるまで、経済が統制されることになった。1939(昭和14)年9月には、第二次世界大戦が始まり、時の阿部信行内閣は「不介入」を声明した。戦争により国際物価は急騰し、国内物価にも波及、また大戦歓迎ムードにより株価が急騰したため、国家総動員法のもと、九・一八停止令(賃金統制令・価格等統制令)が公布され、賃金・物価が同日の水準で固定化された。
このことは科学機器業界にも大きな影響を与えた。科学機器は同じ製品でも業者ごと、また時期ごとに価格は異なっているため、凍結時点の実績価格で凍結されてしまったことにより、営業に障害が生じた。また見積書の作成においては、凍結時点の価格と照合する必要があり、それは非常に煩雑な作業となった。
その上、資材の入手は軍関係以外では困難となり、ヤミ値で購入するケースが増えていった。そのため、原価が高騰し、科学機器業者は厳しい経営を余儀なくされた。
翌年(1940年)、九・一八停止令の改定が行われ、当初は1年だった有効期限がさらに1年延長された(1941年の改正では無期限となる)。そのため、東京理化学器械同業組合は、組合内に協定価格委員会を作り、そこで協定価格を決定し、業者の営業活動の支援にあたった。その後、科学機器の価格は商工省による公定価格へとさらに統制されていった。
●科学技術の軍事研究への動員
この頃、日本の政府軍部は戦争遂行のために国家のあらゆる資源を総動員し、人文・社会・科学あらゆる分野において学術動員を働きかけた。民間研究機関の軍事研究への動員も始まり、1940(昭和15)年に財団法人科学動員協会が設立された。
1941(昭和16)年、第二次近衛内閣のもとで「科学技術新体制確立要綱」が閣議決定され、翌年に公布された。これは、科学技術をもって国防国家を構築するために、研究行政機関である技術院の設置、科学技術研究機関の総合整備、科学技術審議会の設置などを実施しようと策定されたものであった。
のちに科学動員協会は技術院の外郭団体となり、研究資材斡旋機関としての役割も果たした。このため、科学機器業界に製作用の資材が増配され、一時的に業界を潤した。
●東京理化学器械工業組合の設立
日中戦争が長期化するにつれて、日本経済は物資不足や外交関係の悪化により、深刻な事態を迎えていく。特に、米国との対立による影響は大きく、1940(昭和15)年に日本への屑鉄・航空機用燃料などの輸出が制限され、米国からの資源に依存していた日本の軍需産業は大きな打撃を受けた。その後、日独伊三国同盟の締結があり、さらに日米関係は悪化し、米国の禁輸措置は石油、屑鉄や鋼鉄などさまざまな重要資材に広がった。
1941(昭和16)年6月には、ドイツとソ連との戦争が開戦し、ドイツからの輸入ルートが絶たれ、さらに日本経済は苦境に陥っていった。
そうした中、同年8月に発令された重要産業団体令により、多くの中小企業が統合された。
統制と経済状況が厳しい中にあって、東京理化学器械同業組合は協定価格の策定、資源の割り当てなどの業務を遂行していた。
同組合とは別に、製造業者を中心に構成された「東京理化学器械工業組合」が1941(昭和16)年に設立された。理事長には山越長七氏が就任した。
加入するには製造業者であることが条件であったが、資材を下請に供給して製作させている、あるいは店先で組み立てて販売しているという形態でも製造業者として認められたため、同業組合の大部分の組合員が工業組合に加入した。
●企業合同の強制に対する東京理化学器械工業組合の動き
商工省の原材料配給見込数量を基準として、企業の合同及び整理計画が進んでいった。理化学機器工業の整備にも及び、1941(昭和16)年11月8日、「理化学機器に関する品種別工業組合設立」の指示が商工省から東京府知事宛てに通達された。
その内容は、組合名を「日本理化学機器工業組合」とし、組合員の資格として、下請工場として親工場に納入するものを除く年生産額8万円(現在の約3,200万円に相当すると考えられる)以上、および使用職工数20名以上であること、というものであった。これらの条件は当時の業界の実情や組合員の実態からみても非常に厳しく、このままでは一部の組合員で営業が立ち行かなくなることが予想された。
そこで、東京理化学器械工業組合は打開策として、「資格を現在持っていないものについては、ただちに商法による同業の法的合同化を図る」「合同または合併が不可能なものについては、登録協力製作要綱により、組合員の協力工場として一定期間作業させる」の2項目を骨子とした「日本理化学機器工業組合設立に関する東京理化学器械工業組合整理案」を作成し、東京府に提出した。この整理案は、1941(昭和16)年12月2日に東京府から認可された。
●太平洋戦争開戦。東京理化学器械工業組合から日本理化学機器工業会へ
1941(昭和16)年12月8日、日本がハワイ真珠湾に攻撃をしかけ、ついに米英両国との戦争、いわゆる太平洋戦争に突入した。
翌年1942(昭和17)年から企業整備令が数次にわたって公布され、多くの中小企業が解体されていった。この中にあって、東京理化学器械工業組合は、先の東京理化学器械工業組合整理案をもとに企業合同を進めていった。
その結果、組合員のうち41名が12社に統合され、有資格企業として1942(昭和17)年、東京府から認可を受けることができた。このことは戦時下にあって、業界を照らす一つの光となった。
この後、東京理化学器械工業組合は、商工省の指令に基づき、全国組織として「日本理化学機器工業組合」に改組した。
●日本理化学機器工業組合から日本理化学機器工業統制組合に改組
太平洋戦争の戦線は拡大し、1942(昭和17)年1月マニラ占領、2月にはシンガポールを占領するなど、日本は度重なる戦果に歓喜していた。しかし同年6月にミッドウエー海戦にて大敗し、年末にはガダルカナル島から撤退するなど、徐々に戦局に陰りが見え始めた。1943(昭和18)年になると、日本軍は各戦線で敗戦に転じた。しかしながら、報道規制により国民のほとんどが事実を知らないままだった。
1943(昭和18)年10月に、軍需会社法が制定され、11月には軍需省が発足した。これにより、民間企業は統制令による自主統制から国家によって直接、統制されることになった。
いよいよ物資の欠乏が深刻化してくるなかで、資材統制が一層強化された。そのため、1944(昭和19)年7月、日本理化学機器工業組合は解散、日本理化学機器工業統制組合が設立されることになった。
●東京理化学機器同業組合の解散
日本理化学機器工業統制組合の設立を機に、同じく1944(昭和19)年7月17日、東京理化学器械同業組合が解散した。
1919(大正8)年に科学機器業界の母体組織として設立され業界の発展に貢献してきた組合は、25年の幕を閉じた。解散式は、同日午後1時より日本橋の実連会館講堂で行われた。
当時の役員は、山越長七(組合長)、山川英蔵、石渡章元、須賀孟伯、筒井末造、入江照一、村橋素一郎、松永倉吉、橋本謙治、高橋安太郎、伊藤達也、中村久助、森川惣助(2代目)、石山静雄、田中陽太郎、鈴木惣八(2代目)、千野一雄の各氏であった。
組合書記であった丸山宗太氏は、引き続き日本理化学機器工業統制組合の書記を務めた。
●太平洋戦争の終戦
1944(昭和19)年の初めには、インパール作戦の失敗、7月にはサイパン島で日本軍が玉砕し、南方の島々はアメリカ軍の支配下となった。これらの島を足掛かりに、アメリカによる日本全土への空襲は激しさを増していった。
特に東京は、1945(昭和20)年3月の東京大空襲、加えて4月、5月の空襲により、焦土と化した。科学機器業者の多くは、工場や事務所を失った。また、業界に割り当てられる資材もなくなり、日本理化学機器工業統制組合はその機能を失っていった。
そして、8月6日広島、9日長崎に原子爆弾が投下。核分裂反応による強烈な熱線と爆風は、数十万人の命を奪った。皮肉にも当時の最新科学技術の結集は、史上最悪の大量破壊兵器を生み出してしまったのである。
8月14日、日本は、全日本軍の無条件降伏等を求めたポツダム宣言を受諾。翌日15日には、昭和天皇の玉音放送により、日本の降伏が国民に伝えられ、日中戦争を含めた太平洋戦争は終戦を迎えた。