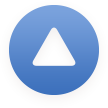●ミュンヘン会議(第1回国際科学機器団体会議)
1985(昭和60)年のACHEMA’85の会期中に、SAMA会長から矢澤連合会会長に、同じ業界の団体として情報の交換及び親交を持つための先進国会議をアメリカ、日本、ドイツ、フランス、イギリスとともに開きたいという提案があった。
そして前述したように、1986年のPITTCONにおける各国の関係者の話し合いを経て、同年にミュンヘンで行われる「Analytica’86」の機会に会議が開かれることになり、SAMAより正式な招待状が届いた。
いわば、先進国科学機器団体のサミットに日本科学機器団体連合会が参加することになったのである。これは、PITTCON及びACHEMAの出展において、日本の科学機器業界の国際化に向けた活動が高く評価されたからだといえよう。
ミュンヘン会議(第1回国際科学機器団体会議)は、6月4日ミュンヘン市内のフィア・カーレスツァイテンホテルで開催された。会議には、矢澤連合会会長、東京科学機器協会から三田村理事(貿易委員長)、大阪科学機器協会から西山・増田両理事、通訳兼記録係として矢澤英人氏(東京科学機器協会・科学機器貿易研究会幹事)が参加した。また、このミュンヘン会議では分析機器を中心に討議されることが推測されたため、日本分析機器工業会の賛同を得て、同会の木村専務理事、ヨーロッパ島津の駐在員作田憲三氏も同行いただいた。
各国からは以下の団体が参加した。
【出席団体】
イギリス GAMBICA(英国制御・自動化機器工業会)2名
イタリア ASTRU(イタリア分析・医用機器連合)
フランス APFIL(フランス分析機器振興会)1名
CHAMBRE SYNDICALE(フランス科学機器製造及び販売連合会)1名
CIF(I フランス製造販売連合会)2名
※主催者であるアメリカは担当者の体調不良のため欠席、
西ドイツは遅れて出席。
会議は午前9時から午後1時すぎまで、休憩を入れずに行われ、以下に示す課題が討議された。
【討議された課題】
①統計作成
製品の名称、分類の統一によって、製品統計を共通の手法によって作成する。このための協力を各国政府に働きかける。
②関税問題
日本より、日本は4月より輸入関税率はゼロとなるが、アメリカは5.9%から13.8%に上げ、欧州は6.8%の関税を課している、改善を図るべきだと提案。アメリカの欠席により次回の会議で討議することになる。
③COCOM問題
共同で業界の利益になるように交渉する。国別の輸出入の制限はないかどうかを調査する。北欧やスペイン等の他の地域を含めた形を作らないと、世界的な統一を目指す活動は難しいとの指摘もあった。
④装置の安全基準・用語の統一
日本分析機器工業会が現在進めている作業の状況を説明、各国統一して作成すべき重要課題ということで、各国とも同意した。さらにフランスより電気安全、資料の統一化等に的を絞って、作業がしやすいような方法を検討したいと提案され、次回に各国が資料を持ち寄ることにした。当日の夕食会には、ドイツ代表2名(VDF&OI:ドイツ精密機械・光学産業会)が参加し、さらに討議が重ねられた。
その席で、議事録をGAMBICAが作成し、SAMAと協議の上、今後の方針も加えて参加団体に送付する、各団体は会員の意向を調査し回答することが決議された。
しかしながら、このミュンヘン会議における決定事項は、実施されることはなかった。
●業界の国際化進む 日本経済はバブル景気へ
1980年代は、科学機器業界が海外へと積極的アプローチした時期であった。これは会員企業の海外進出がかなりの規模に広がっている現れでもあった。
当時の日本は、自動車・家電のハイテク産業を中心として欧米への輸出が伸び、アメリカを中心とする諸外国貿易摩擦が拡大した。しかし、1985(昭和60)年のプラザ合意により円は対ドルで大幅に高くなり、景気は後退した。これに対し積極的な内需振興策がとられ、 1986(昭和61)年の末には景気は回復に向かった。この過程において、株価や地価などの資産価格が急騰し、いわゆるバブル景気となったのである。
こうした中、全科展が1984(昭和59)年に記念すべき20回目を迎えた。10月15日~ 19日までの5日間、晴海の会場で行われ、出展者数350社、小間数1,143小間、来場者数6万1,995名という大盛況のうち幕を閉じた。
また、海外メーカーの在日駐在員の参加は30カ国に及んだ。また、1988(昭和63)年に開催された第22回の全科展では、海外からの来場は、41カ国、721名に上った。こうした数字からも国際化の一端を読み取ることができよう。企業のR&D活動が盛んに好況の日本において、科学技術も新しい段階へと進んでいた。
1985(昭和60)年12月、科学技術会議が、今後10年間においてとられるべき科学技術振興政策の基本を示す「科学技術政策大綱」を当時の中曽根康弘内閣に答申し、1986(昭和61)年3月に閣議決定された。この中で強調されていることは、大学及び国立研究機関の基礎研究、基礎的先導的研究開発が国際的にも重要性を増しているということであった。これは、日本が独自の研究を行わずに海外の基礎研究の成果を利用している、いわゆる「基礎研究ただ乗り」だと国際的な批判を浴びていたことが背景にあった。また、産官学の研究交流を促進するための制度の確立も要望されていた。
このころの日本の研究費は年々増加傾向にあった。国の研究費の増額はわずかであったが、民間では大幅な増額を示していた。特にエレクトロニクス、バイオテクノロジーの産業では、し烈な生き残りをかけて研究開発に投資を活発に行っていたのである。
いわゆるR&D(研究開発)という名のもとに、主要企業では投資がR&D活動に特化するまでになり、1986年には6兆1,058億8,600万円だった研究費は、91年には、9兆7,161億9,500万円となった。1990年のころには設備投資額と研究開発額が逆転するという現象を引き起こした。ただし、この原因の一つには、かつてのような重化学工業の設備投資が減り、FMS(フレキシブル生産システム)といった多品種・小ロット生産に対応した生産システムの導入によって、設備投資に構造的変化が起こったことも考えられる。
科学機器産業は、R&D投資額の増大という環境の中で、それに応じて業界の規模を拡大し、構造を強化していった。そして、研究支援産業として位置づけられていったのである。
●初の消費税 業界の努力によりスムーズに導入
1989(昭和64)年1月7日、昭和天皇崩御によって昭和という激動の時代は終わりを告げ、平成の時代となった。同年の4月には初の消費税(税率3%)が施行された。この消費税は、今後、国民生活と企業活動に大きな影響を与えていくことになる。
長年の議論を重ねた上での導入だったため、科学機器業界においてもその準備を整えていた。東京科学機器協会は、日本科学機器団体連合会傘下の全国会員の賛同を得て、外税方式の「消費税の転嫁の方法及び消費税についての表示方法に係る共同行為に関する協定」を公正取引委員会に提出、許可を得た。これにより、業界内の意思の統一を図り、業務に齟齬を来したり、ユーザーに迷惑をかけたりすることのないように努めた。
このように科学機器業界に限らず、各産業の業界団体が消費税への対応に努力したために、また好況も相まって、消費税は比較的スムーズに実施されたのである。
●輸入促進ミッションの派遣
日本経済は好景気が続き、岩戸景気に迫る勢いであった。また貿易収支は大幅な黒字を示していた。一方で、アメリカをはじめヨーロッパの諸外国の経済は減速傾向にあった。
そのため、貿易に不均衡が生じ、その対策として日本は1990(平成2)年、製品輸入促進税制の導入など輸入を促進する政策をとった。その結果、1990年の輸入額は1985年に比べてドルベースで1.8倍に達し、中でも製品輸入額が急速に伸びていた。
日本科学機器団体連合会においても、かねてより協力関係にあったジェトロより、連合会が予定していたAnalytica’90の視察団を輸入促進ミッションとして派遣したいという申し入れがあった。連合会ではこの申し入れを受けて、早速ミッションの編成に着手した。
東京、大阪、京都、信越の各地区協会から28名、加えてジェトロの随行職員1名、添乗員1名の視察団が結成された。団長は東京科学機器協会の下平武理事、副団長は東ソーの馬場信行氏であった。5月8日から11日までという短期間の旅程であったが、Analytica展における輸入促進ミッションはいくつかの成果を上げることができた。それは、具体的な成約が数件あったこと、日本での代理店を探している出展者に巡り合い、一人は日本のマ人々で賑わう会場会場の看板派遣されたミッション一同ーケットを研究するために秋の全科展に参加する意思を示したこと、などであった。特に代理店を求めるメーカーの発見は、ほとんどのメーカーが日本の代理店がすでに決まっている中での成果であった。
さらに1991(平成3)年6月に開催されたACHEMA’91展においても、輸入促進ミッションのチームが視察団に加わった。この展示会では、ジェトロ・連合会共同ブースを有効に活用して、所期の目的を遂行することができた。また、ジェトロの尽力によって、ジェトロ主催の晩さん会で、GAMBICA、BLWA及びフランスのSalon du Laboratoireの代表と懇親をもつことができ、ミュンヘン会議以来、滞っていた交流を再開することができたのである。
その後、1993(平成5)年、1994(平成6)年のアメリカのPITTCONにおいても輸入促進ミッションが派遣された。アメリカの現地メーカーとの交流を深め、多くの課題を日本に持ち帰った。
1993年の柴田連合会国際委員長の報告では、米国では製品化されていない多くの優れたシステム、センサーがあり、これらの技術や特許を買い取り、日本で製品化したほうが米国で製品化するよりも時間的には早くなる可能性があると述べている。
ちなみに、こうした輸入促進ミッションは、ベルリンの壁崩壊からドイツ再統一(1989年~1990年)、湾岸戦争(1991年)、ソビエト連邦の崩壊(1991年)など、世界が混乱、そして新たな国際関係へと突入した時代に行われたのである。
●台湾・台北市儀器商業同業公会の交流
欧米諸国のみならず、アジア地域との交流も盛んになっていった。1980(昭和55)年8月、大阪科学機器協会は、台湾の台北市儀器商業同業公会(理事長・童揺轍氏)の主催で開催された「台北市第1回儀器展示会」に視察団(15名)を派遣して、台湾の科学機器業界との交流を深めることに成功した。
また、台湾の市場には日本ではあまり見られない欧米の製品が多数出品されているのに驚き、有益な視察旅行であったことが報告されている。
この交流がきっかけになり、翌年に大阪科学機器協会が開催した「第8回科学機器展」には、台北市儀器商業同業公会からは40名の会員が来訪、友好を温めたことから次の台北市第2回儀器展示会にも視察団を派遣することにつながっていった。
第2回儀器展示会は、1983(昭和58)年8月に開催され、東京科学機器協会と大阪科学機器協会が視察団を派遣した。この展示会は、出展社数は180社、小間数は600小間という盛況ぶりであった。台湾の燃える意欲を感じさせる展示会であったことが報告されている。
展示製品は、台湾メーカーの製品もあったが、日本のメーカーも含めて海外20数カ国の製品が並べられていて、視察団の言葉を借りるなら「海外展の縮図を見るの感」であったという。
1987(昭和62)年7月開催の第3回台北市科学機器展には、東京科学機器協会がSJCグループも含めて90名の研修視察団を、また大阪・東海の科学機器協会が合同で視察団を編成し40名が参加した。さらに、1990(平成2)年7月開催の第4回儀器展示会には、東京50名、大阪32名、東海14名という大視察団が派遣された。
どちらの視察団も現地で盛大な歓迎を受けた。特に第4回の展示会での祝賀パーティでは、視察団全員が招待され両国代表の挨拶で始まるなど、交流が一段と進んだことを示した。
1992(平成4)年9月に開催された第5回台北国際儀器展は、台北市儀器商業同業公会と中国化学会の共催で開催された。この展示会にも、日本より視察団が派遣され、高雄市の楠梓加工区の工場見学もともに実施した。
この展示会の祝賀パーティにおいて、日本科学機器団体連合会会長の入江照四氏が同年に開催される第24回全科展に台北市儀器商業同業公会の会員を招待することを述べ、両国の交流の新たな転機となったのである。
●日・台・韓 3カ国科学機器業界団体交流会議の実現
1994(平成6)年11月8日~ 11日までの4日間、東京晴海、東京国際見本市会場において、第25回全科展が開催された。同展に来場した外国人813名のうち、台湾176名、韓国230名と半数を占めていた。台湾・韓国の科学機器業者が、日本の科学機器に対して並々ならぬ関心を抱いていたかがわかるであろう。
全科展の初日には、日本、台湾、韓国の科学機器業界団体の役員懇談会が開催された。台湾からは台湾の各地区儀器商業同業公会を代表して台北市儀器商業同業公会連合会の陳見理事長をはじめ10名、韓国からは韓国科学機器工業協同組合を代表して、Hong Soon Jick,Presidentはじめ11名、日本からは入江連合会会長はじめ18名が参加した。
この日の懇談会では、今後も3カ国の交流会を継続していくことが決定された。3カ国という小さな単位ではあるが、交流が組織的な活動に進展してきたことに期待が高まっていったのである。
この日・台・韓3カ国科学機器業界団体交流会議は、1995(平成7)年の台北市第6回台北国際儀器展で2回目を、同年にソウルで行われた韓国国際科学機器展で3回目が催された。
4回目は、1996(平成8)年10月22日から25日までの4日間、東京ビッグサイトで開催された第26回全科展の初日に行われた。日本科学機器団体連合会からは入江会長ほか12名、台湾からは台北市儀器商業同業公会連合会の陳見理事長ほか3名、韓国からは韓国科学機器工業協同組合の郭秉珍専務理事ほか2名が参加した。
この会議では、前年ソウルで開催された交流会議に出席した東京科学機器協会の勝崎宣夫理事からの提案で、組織として活動を目指すことになり、ASIC( Asia Scientific Instrument Conference:アジア科学機器業界団体会議)という組織名が決定した。このASICが、アジア各国に交流の輪を広げていく中心軸の役割を担うことになり、定期的に開催されるようになった。
1998(平成10)年10月27日から30日まで開催された第27回全科展では、開幕日に第7回ASICが開催され、日本(日本科学機器団体連合会)、台湾(台北市儀器商業同業公会、高雄市儀器商業同業公会)、韓国(韓国科学機器工業協同組合)に加え、新たにタイ(SCIENCE AND TECHNOLOGY TRADE ASSOCIATION:STTA,THAI)の加盟が満場一致で承認された。
そして、2000(平成12)年11月28日から12月1日まで行われた第28回全科展では、タイを加えた4カ国によるASICが開催され、新たな一歩を踏み出した。
さらに、2001(平成13)年8月16日から19日までの4日間、台北で開催された「第8回台北国際儀器展」の会場で、第9回ASICが開催され、加入47カ国の科学機器団体のトップ会議でASICの綱領を定め、採択した。
●初の海外主催展 ベトナムにおける展示会の開催に向けて
この頃の国際化の流れの中には、ベトナムとの交流もあった。まずは、1996(平成8)年の第26回全科展開催時に、会員企業の丸菱バイオエンジが、単独でベトナム総合大学応用微生物学部教授の阮麟勇氏一行のベトナム・ミッションを招待し、交流を図った。阮麟勇氏は、「ベトナムの科学者と日本の科学者が良い関係を保っていることを希望している。立派な展示会を見せてくれてありがとう」というコメントを残し、帰国した。
阮麟勇氏の要望もあって、翌年の2月にはベトナムの研究機器を把握するために、丸菱バイオエンジの山縣社長と古江サイエンスの古江社長が訪越。ホーチミン、ニャチャン、ハノイの研究機関11カ所を訪問、ベトナムの研究機関の現況をつぶさに観察した。この視察旅行により、ベトナムにおいて展示会を開催する可能性が生まれ、有志によりその実現に向けて活動がスタートすることになった。
同年12月には、ベトナムで開催予定の科学機器展に出品を希望するメーカー有志6社8名で視察団を編成、ホーチミン、ニャチャン、ハノイの研究機関・大学等16カ所を訪問した。
この訪越の目的は、直接ユーザーに会って話を聞くことで、ベトナムの研究機関における科学機器の需要動向を把握して、どのような製品を展示すべきかなどの調査をすることであった。
また、ベトナム科学技術環境庁及び同庁CHUSHAE次官を表敬訪問、駐ベトナム日本大使館ODA担当の池田一等書記官を訪問し、展示会開催の環境づくりに努めた。
●“SIS HANOI ʼ98”、 “JSIE Vietnam ʼ99”を開催
1998(平成10)年4月14日から17日の4日間、ついにハノイ科学機器展(“SIS HANOI’98”)が開催された。山縣出展団団長をはじめメーカー有志8社による主催で、日本科学機器団体連合会は後援を行った。開催場所はハノイの国立衛生・疫学研究所(現・パスツール研究所アジアセンター)のコンファレンスホールで、2階の講堂では疫学衛生学会が行われていた。これは事前に学会と連動して開催しようと準備をしていたためである。
会場設営日に山縣出展団団長らは、ジェトロのハノイ事務所を訪れ、次回の科学機器展にジェトロの支援を打診すると、開会の日にハノイ事務所長が来場し、次回開催の礎となった。
また出展団一行は、展示会が終了した翌日に、CHU TUANNHA科学技術環境大臣と懇談を行った。
その後、2回目の展示会に向けて、日本科学機器団体連合会として組織体制を整備することになった。準備委員会を発足させ、ジェトロ・ハノイ事務所との連絡を密にしながら、準備を進めていった。そうした経過を経て、ハノイ科学機器展はジェトロ、日本科学機器団体連合会、ベトナム技術輸出入公社(Tec-hnimex)の3団体が主催となり、さらにベトナム科学技術環境省(MOSTE)、ベトナム国立総合大学(VNU)、ベトナム生物学協会(VSB)の3機関の後援を得て開催されることになった。
ちなみに、当時日本とジェトロ・ハノイ事務所との連絡は主に電子メールで行われていた。情報通信技術の発達がこうした活動を支えてくれていたといえよう。
そして、1999(平成11)年、10月18日~ 20日までの3日間、1999年ハノイ科学機器展(JSIE Vietnam ’99)は、ベトナム国立大学カンファレンスホールで盛大に開催された。製品出品会社21社・27小間、カタログ出品会社17社の参加で、来場者は約1,000名であった。連合会では、入江会長を団長とする代表団を派遣した。
開会式には、ベトナム側から、ベトナム科学技術協会連合会会長のHoaug教授(ベトナム生物学協会会長・越日友好協会会長)、ベトナム科学技術環境省Nguyen次官、ベトナム国立総合大学Dung教授(ベトナム生物学協会事務局長・国会議員)をはじめ招待された関係者が出席した。
日本側からは、中村武駐ベトナム日本国特命全権大使、安楽岡武書記官、朝倉俊雄ジェトロ・ハノイ事務局長、セミナー講師団(吉田敏臣大阪大学教授・日本生物工学会会長はじめ6名)、日本科学機器団体連合会代表団(団長・入江会長、平井副会長、西山理事、岡野理事)で、日越合わせて250名の出席を得て、盛大に挙行された。
●バブル崩壊のなか「全科展」の出展社増加
1990年代は科学機器業界にとって国際化の時代であったが、日本経済にとっては混迷の時代だった。いわゆるバブル崩壊の時代である。バブル崩壊により、1973(昭和48)年から続いた安定成長期は終焉を告げた。そして、失われた20年と呼ばれる低成長期に突入するのである。
科学機器業界も厳しい状況に置かれたが、国や企業の研究開発投資は大きな後退をみせることはなかった。特に国の科学研究費は、基礎研究の拡充を国際的に求められているために、92年、93年には大幅な増加を示している。このように、科学機器業界は基礎的なマーケットベースにおいては、景気後退の影響が少ない業種だといえる。
しかしながら、1992(平成4)年11月に開催された第24回全科展は、これまで前年比プラスの来場者数を記録していたが、初めて6%のマイナスに転じた。全科展の歴史のなかで、最も厳しい経済環境のもとでの開催であったことのあらわれであろう。
ただし、6%という軽微な減少でおさまったこと、出展社数が前回よりも6.5%増えたことは、実行委員会の努力もさることながら、業界が不況に強いという特性をもっているからだといえよう。
●「第25回全科展」において、特別企画「科学機器のあゆみ」展を開催
1994(平成6)年に開催された「第25回全科展」において、特別企画「科学機器のあゆみ」の展示コーナーを設け、歴史的に貴重な科学機器、文献、カタログなどを一堂に集め展示した。
主旨は、“温故知新”にあり、過去にこだわるものではなく、むしろ未来への展望とこれからの業界の発展を期するものであった。
本展示は東京科学機器協会の50周年記念行事の一環として行われたものであり、特別展示Aゾーンでは科学機器の進歩と発展の紹介、Bゾーンでは業界団体の創成期及び戦後50年の事業活動を紹介した。バブル崩壊後の厳しい経済環境にあって、来場者の好評を得ることができた。
●科学技術基本計画にみる21世紀への期待
1995(平成7)年11月15日、科学技術基本法が公布、施行された。これには、国が「科学技術創造立国」を目指し、科学技術振興のための基本的な計画を決め、国や地方自治体は振興に責任を持つこと、国は必要な資金の確保を図る措置を講じることが定められている。科学機器業界にとっても待ちに待った法律であった。
翌年1996(平成8)年8月にはこの基本法に基づいて、「科学技術基本計画」が実施に移され、5年間で17兆円の研究投資が実施されることになった。日本におけるバイオ技術、情報通信技術の研究開発を推進する上での原動力となった。
引き続き、2001年度から5年間の第2期科学技術基本計画が策定され、科学技術は社会の持続的発展の牽引車、人類の未来を切り拓く力だという基本理念が示された。特に、ライフサイエンス分野、情報通信分野、環境分野、ナノテクノロジー・材料分野に重点を置き、優先的に研究資源を配分するとした。研究投資総額は1期よりもさらに多く、24兆円と計画された(ただし前提として対GDP比1%、GDP名目成長率3.5%)。科学機器業界としては、この計画を高く評価し、21世紀に向けて、さらなる発展への期待が高まっていった。
●福利厚生制度の確立
科学機器業界の企業のほとんどは中小企業であり、単独で社会保障制度を運用することは難しかった。しかし、福利厚生制度の充実は健全な企業づくり、延ひ いては業界づくりに必要であった。そこで日本科学機器団体連合会では1997(平成9)年2月に、団体の福利厚生制度の一環として運営されている団体保険を導入して、「日本科学機器団体連合会グループ保険」を作り、会員企業の加入を勧めた。福利厚生制度の充実を図るための支援も、日本科学機器団体連合会の重大な役割となっていった。
●日本科学機器団体連合会 創立55周年記念式典を挙行
2000(平成12)年、日本科学機器団体連合会は、創立55周年を迎えた。6月16日に記念祝典と祝賀会を東京都港区のホテルインターコンチネンタル東京ベイにおいて挙行した。全国各地区協会の役員、および創立時からの会員、通商産業省、科学技術庁、日本化学会をはじめ、関連諸団体及び報道機関を招待し、出席者数は約200名にのぼった。
日本科学機器団体連合会会長、入江照四氏は式辞において、感謝を述べるとともに創立時の状況や科学機器業界の現状、連合会の活動を紹介した。
現在の科学機器業界は、エレクトロニクス、バイオテクノロジー、新素材、地球環境保全などの新技術開発とその支援のため、各種多様の機器を供給して、大きな成果を収めております
<中略>
そして、本会は国の施策に沿って科学技術の振興に寄与するため、全国での展示会の開催・刊行物の発行を通じて、科学機器の普及に努めているほか、各種の研究支援活動を展開し、確実に成果を上げております。一方、海外に向けては、日本製科学機器の優秀性を広く世界に紹介するとともに、輸入促進にも力を注いでおります。
また、最近は、海外の業界団体との交流も頻繁に行われるようになりました。特に、アジアにおいては、台湾、韓国、タイなど、各国の業界団体と定期的な会議の場を持って、情報交換と研鑽に努めているほか、相互交流を深めております。この活動は、アジア地域における各国の技術開発力を支援し、育成することで、ヨーロッパ、アメリカと並び、アジアの業界を世界3極の一つに育て上げようという、大きな構想のもとに展開されているもので、現在、着々とアジアマーケットの土台造りが進められております。
技術面では、多様化するニーズに対応して行くために努力を傾けているほか、JIS、ISO、IEC等の規格制定や見直しに協力するなど幅広い活動を展開しております。
記念式典では、通商産業省大臣 深谷隆司氏、科学技術庁科学技術振興局長 越智謙二氏、日本化学会会長 村橋俊一氏(肩書はすべて当時)より祝辞が贈られた。各祝辞では、来るべき21世紀に向けての課題を示しながら、科学機器業界、延ひいては連合会に期待を寄せる言葉が強調されていた。また、同式典において、初めて通商産業大臣表彰と通商産業省(現・経済産業省)機械情報産業局長表彰が行われた。
入江照四連合会会長、櫻木惇雄相談役、平井賢一副会長が大臣表彰を、成瀬謙三相談役、吉田信太郎相談役が局長表彰を受けた。
●連絡協議機関から執行機関へ
この記念式典を契機に、連合会はその組織を連絡協議機関から執行機関へと大きく変えることになった。これは、国際化、ボーダレス化の流れに対応できる組織の確立が急務となってきたからである。
具体的にいうと、連合会組織が、諸外国の動向のみではなく、国内、特に産業政策上の標準化や規格、国の施設をはじめ関連学会の諸活動等の情報を的確に把握し、それらの情報を会員にフィードバックできる組織であること、そしてこれらの情報に基づいて政策を策定し、これを実行できる組織でなければならないのである。
●日本科学機器団体連合会55年史を刊行
2001(平成13)年3月、『日本科学機器団体連合会55年史』が55年周年記念事業の一つとして、あらためて業界の歴史を振り返るべく刊行された。当時の会長の入江照四氏は、この55年史について、次のように述べている。
55年史が私達に教えますことは、業界団体の在り方です。<中略>過ぎ去った日々の単なる記録ではないのです。今後私達が、科学機器業界の発展を図るための知恵の宝庫だということを認識されて、55年史を繰っていただければ、と思っているところです。
(「科学機器」2001年3月号より)
55年史では、明治時代の理化学器械の黎明期、1919(大正8)年1月の東京理化学器械同業組合設立から日本科学機器団体連合会創立55年記念式典までの歴史が綴られ、また各地区の科学機器協会の活動も紹介された。
同年史は、各地区科学機器協会の全会員をはじめ関係官庁・学会・関連団体・公立の主要図書館等に配布され、発行数は1,700部であった。
●20世紀から21世紀へ―業界をめぐる動き
21世紀に入り、前述したように第2期科学技術基本計画(2001 ~ 2005年)では、5年間で24兆円という、前期に増した科学技術予算が計上された。まだバブル崩壊後の不況を引きずる世の中にあって、国の科学技術政策に依処している科学機器業界としては、干天の慈雨にも似た朗報であった。
そもそも科学機器業界は研究支援産業として生まれたが、この頃になると、科学機器は新技術産業を下支えする産業機器としても拡大していった。例えば、1990年代後半からパソコン、インターネット、携帯電話などが企業そして個人に急速に浸透し、いわゆる情報技術(Information technology、IT)が発展してきた。このことは科学機器業界にも大きな影響を与えた。特に科学機器の技術をベースにした生産技術は情報技術を支える半導体産業に活用され、科学機器業界にとっても重要なマーケットとなったのである。
2001(平成13)年には、「ITの恩恵を日本国民全員が享受し、国際的なIT競争力をつけること」を目的に、「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部)」が内閣に設置され、巷では「IT革命」という言葉が躍り、この年の新語・流行語大賞を受賞した。
連合会でもIT時代に対応すべく、第28回全日本科学機器展では、前第16版同様に「2001/2002科学機器総覧(第17版)」印刷版とともにCD-ROM版を配布した。さらにWebサイトにも総覧情報を公開、アドレスは「www.soran.net/」と総覧公開のための独自のドメインを取得した。
その後、2002(平成14)年の科学機器総覧からCD-ROM版をやめて印刷版とWeb版の2本立てで発行された。また、Webサイト未開設の企業を対象に、東京科学機器協会ではWebサイトの開設支援のための説明会を実施し、会員企業のIT化のサポートに努めた。
その一方で、海外向けに1958(昭和33)年から発行された科学機器の英文ガイドブックの印刷版は、2002(平成14)年の発行で最後となり、Web版のみとなった。インターネットによるグローバル化によって、海外ユーザーへの情報提供はWeb版で十分に対応可能だからである。これも時代の流れに対応した結果だといえよう。また2000年初頭は、ヒトゲノム計画においてヒトゲノムの解読作業が完了し、バイオ分野がより脚光を浴びてくる年代でもあった。
ヒトゲノム計画(Human Genome Project)は、ヒトのゲノムの全塩基配列を解析するプロジェクトで、1990(平成2)年に米国のエネルギー省と厚生省によって発足し、日、米、英、仏、独、中の 6 カ国 20 研究センターから構成される「国際ヒトゲノムシーケンス決定コンソーシアム」による国際的な取り組みである。
2001(平成13)年にはヒトゲノムの下書き版(ドラフト版)が発表され、2003(平成15)年に完了した。ゲノム情報の解明により、生命科学分野の研究開発において、新しい研究システムが求められるようになった。そのため、科学機器業界においても新しいマーケットが創生され、分析機器をはじめとするバイオ関連機器が重要な存在となってきたのである。同年の第18回科学機器展(大阪科学機器協会、日本工業新聞社共催)では、「バイオフォーラム 2001 OSAKA」を併催するという、新しい試みが行われた。
●絶え間なく続く国際交流
2001年以降も、全科展を機会に開催されるASIC(アジア科学機器業界団体会議)は回数を重ねていた。また、海外の展示会への視察団の派遣も盛んであり、米国で開催される世界最大級の分析・理化学機器の展示会「PITTCON」や科学機器業界にとって世界で最も大きな展示会、「ACHEMA」(3年に一度開催)への研修視察団の派遣は毎回、行われていた。
2000(平成12)年には、PITTCONとACHEMAの他に、4月10日から16日、ドイツ・ミュンヘンで開催された「第17 回国際生化学・分析・診断・ラボテクノロジー専門見本市(Analytica 2000)」にも視察団が派遣された。また、タイの科学機器業者団体STTAの要請に応じて、同年5月10日~ 14日、タイで開催された「Lab Tech 2000(第2回タイ科学機器展)」(現在、Thailand Lab)に、日本科学機器団体連合会(以下、日科連)として初めての出展を果たした。
タイは、東南アジアでは最も早く科学機器業界が生まれた国であり、1998(平成10)年にASICに加盟している。科学機器展が開催されたということは、タイの科学機器業界がそれほどまでに成長した証だといえるだろう。
日科連のブースでは、同年11月に開催される第28回全日本科学機器展のPR活動を主に行った。初日の夜には、STTA主催によるASIC加盟国業界団体歓迎会が行われ、今回不参加であった台湾を除いた、タイ、韓国、日本の参加者が一堂に会した。この歓迎会において、各国の代表団は情報交換および相互交流を深めた。
参加した会員からは、134社の出品者のうち科学機器の展示は35社程度であったが、“想像していた以上に素晴らしい総合展としてインターナショナルな印象を受けた”という報告があった。
2002(平成14)年9月3日から4日間、中国上海で開催された「Analytica China 2002」にも視察団が派遣された。この展示会は、ドイツ・ミュンヘンで隔年開催されている「Analytica」の中国版で、一回目の開催であった。展示会の視察とともに、島津製作所の中国法人島津儀器有限公司の工場見学、展示会の共催団体である中国科学器材進出口総公司との面談も行われた。中国科学機器関連機関と日科連との関係は、1
976(昭和51)年の訪中石油試験技術交流代表団の派遣、1983(昭和58)年の技術交流訪中代表団の派遣にまでさかのぼり、この視察団派遣が久方ぶりの交流となった。奇しくもこの年は、日中国交回復30周年の年であった。当時、中国経済は急成長の只中にあり、科学研究費の増大などから、科学機器のマーケットも、さらに成長が続いていくと予想されていた。こうした時期に、視察団を派遣し中国市場を垣間見る機会となったことは大きな意義があったといえよう。
●全科展が日科連主催に
東京科学機器協会が開催していた全科展が、2002(平成14)年から日科連の主催となった。さらに2003年には大阪で開催されている科学機器展も日科連主催となり、それぞれ「全科展 in 東京 2002」「全科展 in 大阪 2003」という名称で開催された。
名実ともに全国の各地区科学機器協会、すなわち、全国の会員が力を合わせて “日本の科学機器展を開催する”という意義をこめた改革であった。この改革により、各地区協会が一つの意思のもとに統一され、東の全科展、西の全科展として、業界をあげて活動することを目指したのである。
また、この時から全科展は“見せる展示会”から“交流の展示会”へと転換が図られた。というのも、当時、科学技術創造立国を目指した国の政策もあって、産学官の連携が急速に進展してきており、そうした潮流の中、特に科学機器業界にとっては要である“学”との連携をさらに深めることが全科展においても不可欠であったからである。
全科展が産学官連携の役割を果たすべく、さまざまな取り組みが実施されていった。その一つは、会誌「科学機器」2001年9月号より始まった「科学の峰々」の連載である。この連載に、科学の各分野の権威ある研究者や第一線で活躍している研究者に登場いただくことにより、学会と業界の連携を深め、さらに全科展がより効果の大きい交流の場となることを図った取り組みであった。ちなみに記念すべき一回目は、腸内フローラの研究により腸内細菌学という新しい学問を築いた微生物学者、光岡知足先生であった。
そして、2002(平成14)年11月20日から22日、東京ビッグサイトにて、日科連主催による新方針のもと「全科展 in 東京 2002」が開催された。開催期間はこれまでの4日間から3日に短縮、開場時間を1時間延長し、参加企業の負担を軽減するとともに、来場者の利便性を高めた。NEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)と12のTLO(Technology Licensing Organization、技術移転機関)※が参加、また9つの学会・シンポジウムが開催され、まさに“交流の展示会”にふさわしいイベントが行われた。
さらに11月21日には緊急特別講演として、この年、ノーベル化学賞を受賞した田中耕一氏(島津製作所)による講演が開催された。ノーベル賞受賞が全科展開催直前だったにもかかわらず、この講演が実現されたのは島津製作所はじめ関係者の方々の尽力によるものであった。後述のように、科学機器産業界の一人である田中氏が、新しき全科展が開催された年にノーベル賞の受賞を果たし、さらに全科展の壇上に立たれたことは科学機器に携わる人々にとって、大きな励みとなった。
会期中の来場者数は、5万4,829名で前回を上回り、初の日科連主催の全科展は成功裡に終わった。
※TLO……大学の研究者の研究成果を特許化し、それを民間企業等へ技術移転する法人のこと。産と学の「仲介役」の役割を果たす組織。
●ノーベル賞W受賞
2000(平成12)年のノーベル化学賞に白川英樹氏、翌年の同じくノーベル化学賞に野依良治氏と日本人の受賞が相次ぎ、2002年度のノーベル賞は、2名の日本人が受賞するという、史上初の快挙に日本中が喜びに沸いた。科学機器業界にとっては、この喜びはさらに一層大きなものであった。なぜなら、物理学賞を受賞した東京大学名誉教授の小柴昌俊氏、ノーベル化学賞を受賞した島津製作所の田中耕一氏、両氏の研究は測定技術を高めた結果であり、科学機器が密接にかかわっているからである。
小柴昌俊氏は、「天体物理学とくに宇宙ニュートリノの検出に対するパイオニア的貢献」に対して、ノーベル物理学賞が授与された。この宇宙ニュートリノを検出するための観測装置「カミオカンデ」※には、科学機器業界の多くの企業が参画していたのである。
田中耕一氏は、「生体高分子の同定および構造解析のための手法の開発」に対して賞が与えられ、分析機器つまりは科学機器開発の基礎研究の成果が世界に認められたといえる。田中耕一氏の勤務する島津製作所は国産科学機器の先駆的存在であり、業界の黎明期や戦後の混乱期をその中核で支えてきた企業である。この島津製作所からノーベル賞受賞者が誕生したということは、業界自身の栄誉ともいえよう。ちなみに、田中耕一氏は企業人として日本初のノーベル賞受賞となった。
このダブル受賞は科学技術創造立国を目指す日本に、そして科学機器業界に明るい光をもたらした。
※カミオカンデ……ニュートリノを観測するために、岐阜県 神岡鉱山地下1,000mに設置された観測装置。
●入江照四会長、旭日小綬章を受章
日科連は、2005(平成17)年に60周年を迎えた。同じく60周年を迎えた東京科学機器協会の主催で11月9日、記念式典・祝宴が開催された。その日は、当時の日科連会長・東京科学機器協会理事長である入江照四氏が旭日小綬章を受章した日でもあり、業界にとって二重の慶びとなった。
旭日小綬章は、社会の様々な分野において顕著な功績を挙げた者に授与される、栄誉ある勲章である。この旭日小綬章受章は、入江氏の長年にわたる協会活動への貢献、つまりは科学機器産業の振興・発展に寄与した功績が評価された結果であった。
翌年2006(平成18)年の6月16日には、東京丸の内・東京會舘にて「入江照四氏叙勲記念祝賀会」が開催された。全国の科学機器協会役員、東京科学機器協会会員をはじめ、主務官庁の経済産業省、関係学会、関連団体、報道機関など、およそ360名が参加し、慶賀をともにした。また、経済産業大臣の二階俊博氏(代読 政務官・片山さつき氏)、日本化学会会長の藤嶋昭氏、フジサンケイビジネスアイ社長熊坂隆光氏、衆議院議員の尾身幸次氏(すべて当時)より祝辞が贈られた。
祝典の最後に入江会長は、“このたびの叙勲は科学機器業界団体を代表して自分が受章したという気持ちでおり、この栄誉はとりもなおさず我々の仕事が国に認知され、科学機器産業及び業界が理解されたという思いで感慨に絶えない”という旨の謝辞を述べた。
さらに同年3月には、再び科学機器業界にとって喜ぶべきニュースが舞い込んだ。日科連の副会長であり堀場製作所の創業者である堀場雅夫氏(当時最高顧問)が、米国フロリダ・オーランドで開催された[PITTCON 2006」において、「PITTCON Heritage Award(ピッツコン・ヘリテージ・アワード)」を受賞したのである。PITTCON Heritage Awardは、科学計測機器分野で卓越した功績のある企業経営者を顕彰するもので、国際的に権威のある賞である。同時に堀場氏は、同分野の発展に大きく貢献した功績を後世にわたって称える殿堂入り(PITTCON Hall of Fame)の27人目としても認定された。これは日本、さらにいえばアジア初の快挙であった。
日科連として、この栄誉を祝うべく、有志一同の発起(発起人代表・入江会長)により、同年の11月28日、ホテルオークラ東京にて受賞記念祝賀会を開催、業界はもちろん政官学産から約500 名の人々が参加した。祝賀会では、賞の主宰団体である“Chemical Heritage Foundation ”の President、ArnoldThackray氏をはじめ、業界に関係の深い尾身幸次財務大臣(当時)、文部科学副大臣の池坊保子氏(当時)より祝辞が贈られた。
2006年は、第3期科学技術基本計画(平成18 ~ 22年度)が前期を上回る予算の総額25兆円をもって動き出した年であり、この2つの祝宴により科学機器業界の前途がさらに明るく照らされることになった。
●全会員の実態調査を実施
バブル崩壊後の長期不況に加え、2001(平成13)年9月11日には、アメリカ同時多発テロ事件が勃発、その恐怖は世界経済にも大きな打撃を与え、日本経済は低迷が続いていた。しかし、2002 年初めごろから景気が上向きとなり、その景気回復は2007年まで継続する。この息の長い景気回復をもってして、日本経済は1965(昭和40)年11月から1970(昭和45)年7月までの57カ月間続いた高度経済成長時代の好景気「いざなぎ景気」を超えたといわれた。のちにこの期間の景気は「いざなみ景気」と呼ばれることもあった。
そんな景況の中、2004(平成16)年から2005(平成17)年にかけて、日科連傘下の全会員の実態調査を実施した。もともと会員の実態調査は、東京科学機器協会が1990(平成2)年に初めて実施、その後、1996(平成8)年、2001(平成13)年と回数を重ねてきた。日科連の事業として実態調査を行うに至ったのは、関東地方のみの調査では科学機器産業の実態を把握することができないと判断したためである。
グローバル化が進み、企業活動においては日本全体の科学機器産業の実態を踏まえた上での企業戦略が必要な時代となっていた。また業界団体としても会員企業の実態を知らずして運営することは不可能であった。
調査項目は、
①会員企業の概要、
②経営・営業の実態、
③景気動向、
④経営・営業上の問題点、
⑤組織、福利厚生等の制度、
③情報化への対応
とした。
企業の内部事情に触れることになるため、情報秘匿措置を十分にとった上で調査が進められた。その結果は、2005(平成17)年3月に「会員実態調査報告書」として会員に配布された。
2回目の会員実態調査は、2009(平成21)年に実施された。
2008年のアメリカのサブプライムローンの破綻、アメリカの投資銀行リーマン・ブラザーズの破綻によるリーマン・ショックにより、世界的な金融恐慌が起こっていた頃であった。
日本経済も不況の中であり、特に自動車産業、IT産業といった日本をリードする産業の業績悪化は、科学機器業界にも暗い影を落としていた。しかしながら、その一方で、不況にあっても政府の科学技術政策がぶれることなく、科学技術予算が削減されずに進み、また国の研究開発費も緩やかではあるが増大しているという事実が業界を支えていた。
●初の合同展示会から「JASIS」 へ
2010(平成22)年に入り、18年にわたり日科連会長を務めてきた入江照四氏がその職責を果たし、新しく矢澤英人氏(株式会社ダルトン代表取締役社長:当時)が会長に就任した。
新世代による日科連の事業にふさわしく、同年より社団法人 日本分析機器工業会(堀場厚会長)との話し合いにより、「分析展」と「全日本科学機器展」を共同主催として合同で開催することになった。そもそも日科連では、以前より複数の関連展示会との連携を視野に入れながら、全科展を“アジアのハブ”たる展示会とすることを目指していた。そして、日科連にとって重要な関連団体の一つである日本分析機器工業会と協議を重ねた結果、この合同展示会の開催が決定したのであった。くしくも「全日本科学機器展」は、1960(昭和35)年開催の第1回から50年を数え、また日本分析機器工業会も創立50周年と、両会とも共に半世紀という節目を迎えていたのである。
研究開発・生産技術を支援する“科学機器”をはじめ、分析機器、計測機器および設備・関連製品を一堂に合同展示することにより、出展小間数を増やし、展示内容の充実を図った。また、日本分析機器工業会と共に学会との連携を深め、各種併設イベントの内容も充実させるなど入念な準備が進められていった。
そして、2010年9月1 ~ 3日、初の「分析展2010/科学機器展2010」合同展示会が幕張メッセにて開催された。出展企業・団体数が450、小間数が1,361という、これまでの全科展を大きく凌ぐ出展規模となった。また展示会場は5つのホールを使用し、アジア最大級の分析・科学機器分野の総合展として開催された。
初日には、日科連会長の矢澤英人氏、そして日本分析機器工業会会長の堀場厚氏が開会の挨拶を行い、合同展示会が実現した慶びと感謝の言葉を述べた。3日間に亘り、産学官の各分野から講師を招いたセミナーや講演会、分析展で従来行ってきた新技術説明会、日本化学会主催の理科教育セミナーなど、さまざまなイベントが実施された。
世界経済、もちろん日本経済にあっては、いまだリーマン・ショック以降の不況から脱せず、科学機器産業も同じ状況の中での開催であったが、来場者数は2008(平成20)年の全科展をはるかに上回る2万4,549名にのぼり、盛況のうちに終幕、期待通りの成功をおさめることができた。
この初の合同展示会の成功により、毎年、合同展が開催されるようになった。2012年の開催では、名称を統一して「JASIS」とし、また科学機器総覧も分析機器総覧とあわせて「科学・分析機器総覧」として配布するなど、名実ともに合同展示会となるよう、さらなるコラボレーションを展開していった。
●2011年3月11日、東日本大震災
21世紀となって10年、アメリカ同時多発テロをはじめとして、リーマン・ショックによる世界的な恐慌と厳しい国際状況の中で、日本の科学機器業界も苦境に立たされた。しかしながら、2010(平成22)年の後半には、分析展との初の合同展示会の成功、日本の化学者二人(鈴木章氏、根岸英一氏)のノーベル化学賞受賞と、明るいニュースが業界を照らした。
2011(平成23)年の初めには、世界経済は次第に落ち着きを見せるようになった。また、第4期科学技術基本計画の予算は25兆円という見通しが立ち、業界にとって明るいニュースとなった。この額は、2009(平成21)年9月に自民党から政権交代した民主党政権による国家予算の見直し、いわゆる事業仕分けを乗り越えた結果であった。
さらに言えば、2011年は世界化学年の年であった。世界化学年は、マリ・キュリーのノーベル化学賞の受賞から100年目、また国際純正・応用化学連合(IUPAC)設立100周年にあたるとして、国際連合総会により決められた。この「世界化学年」の旗の下に、日本の化学関係の学協会・諸団体がさまざまな活動を推進していた。
そうした希望の光がさし始めた2011年早春、日科連ではあらたな期待をもって2011年度の諸策定を進めていた。そんな中、自然の脅威が東北・関東地方を襲った。
3月11日、東日本大震災である。三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の地震は、巨大津波を引き起こし、青森県から千葉県までの太平洋の沿岸部において多くの人々の命、そして日常を奪った。加えて、津波と地震動の影響により福第一・第二原子力発電所事故が発生、放射線被害をもたらし周辺住民は故郷を追われた。また、放射線被害やそれに伴う風評被害により、福島県周辺の農業、畜産、漁業などは大きな打撃を受けた。東日本大震災において、死者は1万5,892人、重軽傷者は6,152人、行方不明者は2,574人(2016年1月8日現在)とされ、戦後最悪の災害となった。
また、福島第一・第二原子力発電所事故の影響により、全国の原子力発電所が安全点検などのため稼働を停止、日本全国の電力が不足した。そのため、計画停電が実施されると共に、全国民に節電が呼びかけられた。被災地のみならず、日本全国の企業活動、人々の日常生活にも大きな打撃を与えたのである。
科学機器業界と密接な関係がある研究機関の被害も甚大であった。東北地方、関東地方の177大学、34の独立行政法人・国立研究所の研究施設・設備が損傷し、建物損壊、外壁破損、配管破損、内壁崩壊、施設周辺の地盤沈下、研究施設への立ち入り禁止措置、最先端研究機器の破損など、多くの機関で深刻な影響を受けた。
直接、研究施設・設備に被害を受けなかった大学、独立行政法人、国立研究所でも、計画停電実施や節電への対応により研究施設の稼働を縮小せざるを得ないなど、研究開発活動に多大な影響を及ぼした。加えて、外国人研究者が退職、一時帰国した施設もあったという。
もちろん科学機器業界も無傷ではなかった。日科連では震災後ただちに各地区協会の会員企業の安否確認を行い、被害状況の把握に努めた。津波により工場が浸水した企業、従業員やその家族が犠牲になった企業もあり、業界全体が悲しみに包まれた。しばらくすると、多くの企業が被災地の機器の修理やメンテナンスに奔走するなど、復興に向けて力を注いでいった。
そうした厳しい状況ではあったが、日科連では、震災直後より会員企業に被災地および被災者への義援金をよびかけていた。結果、各地区科学機器協会および会員企業、また会員以外の企業からも賛同を得て、1,690万5,890円という義援金が集まった。また、会員企業の中には、義援金の他に自社製の回診用X線撮影装置や大量のマスク、放射線測定器などを被災地に寄贈したところもあった。
実は、日科連はこれまでも、1995(平成7)年の「阪神・淡路大震災」、2004(平成16)年の「新潟県中越地震」及び「スマトラ沖地震・インド洋大津波」、2008(平成20)年の「岩手・宮城内陸地震」など、その都度、義援金の募集を行い、会員企業から寄せられた多額の義援金を、日本赤十字社を通じて送ってきたのである。こうした活動は、日科連における社会的な責務の一環と考えてのことであった。
東日本大震災直後の9月に開催された「分析展2011/科学機器展2011」は、節電を考慮しクールビズを呼びかけ、業界全体が一丸となって、復興に向けて取り組んでいった。
なお、第4期科学技術基本計画は大震災により大幅に見直され、例年よりも遅れて8月に閣議決定された。第4期基本計画では、①震災からの復興、再生を遂げ、将来にわたる持続的な成長と社会の発展を実現する国、②安全かつ豊かで質の高い国民生活を実現する国、③大規模自然災害など地球規模の問題解決に先導的に取り組む国、④国家存立の基盤となる科学技術を保持する国、⑤「知」の資産を創出し続け、科学技術を文化として育む国、の5つを日本が中長期的に目指すべき大きな目標として掲げ、政策を推進するとした。
また、課題として「技術分野別ではなく社会の課題解決に重点化」、「イノベーション創出に向けた施策を推進」があげられた。なお、目標予算額は25兆円と当初の予算に変更はなかった。
●日本科学機器団体連合会から「一般社団法人日本科学機器協会」へ
2012(平成24)年4月2日、日科連は任意団体から法人化を果たし、「一般社団法人日本科学機器協会」(以下、日科協)が設立された。科学機器業界は新しいスタートを切ったのである。
2008(平成20)年の末に、「公益法人制度改革関連三法」が施行され、従来の主務官庁による公益法人の設立許可制度を改め、登記のみで法人が設立できるようになった。この制度改革が後押しとなり、法人化への意識が高まっていき、2011(平成23)年6月に開催された第66回総会で、組織改革をして法人化することが決定された。
法人化を進める背景には、科学機器業界を取り巻く環境の変化があった。もともとは研究機器であった科学機器は、産業機器の分野、さらには社会機器(環境機器やシステム管理など)の分野にも浸透していった。つまり、産業構造の複雑化、加えてグローバル化といった大きなうねりの中に業界は立たされるようになったのである。そうした時代の流れに対応するための法人化であった。
法人化によって、公益に貢献する活動、会員の利益に資する活動を主軸とした諸活動が可能となり、会員企業に対し、より強力なサポートが提供できるようになった。法人化は、じつに時宜を得たものであったといえよう。
日科連時代では、同会の会員は全国10地区の科学機器協会であって、個々の企業は各地区の科学機器協会に属しており、直接的な会員ではなかった。しかし、新法人のもとでは、各地区の科学機器協会の会員企業は同時に日科協の会員となり、日科協から直接に情報を提供するなど、より効果的に情報交換ができるようになった。また、各地区の科学機器協会は協議機関として中心的な役割を担い、従来と同じように地域に密着した活動を続けていくと共に、日科協の代議員選出や日科協主催の諸事業、関連情報の受・発信などの活動を進めていくことになった。
●日本科学機器協会の設立記念式典・祝賀会を実施
2012(平成24 )年6 月26 日、一般社団法人日本科学機器協会の設立記念式典及び祝賀会が東京會舘(東京丸の内)において開催された。梅雨晴れの中、全国の会員270余名をはじめ来賓に経済産業省・文部科学省、関係学会、友好関連業界団体等の関係機関、報道機関などから、100余名が参列した。
第一部の設立記念式典は、山崎寛治副会長の開会の辞で始まり、国歌斉唱の後、矢澤英人会長が式辞を述べた。式辞では、2年間の任期を振り返り、東日本大震災による影響、円高や新興国の台頭、政治不信など当時の業界を取り巻く厳しい状況が語られたが、新法人の最大の事業活動として「JASIS2012」の開催、「科学・分析機器総覧2012」の発行を紹介、今後の抱負を語った。そして以下のように、力強い言葉で結んだ。
これより以降、本協会の組織体制の強化やグローバル化への対応など、検討すべき課題は山積しており、執行役員には更なる企画力と実行力、また、指導力が求められていると考えます。最後になりましたが、新体制の下、また、ここにお集まりの会員並びにご来賓の皆様のご理解とご支援を賜りながら、科学技術創造立国に向けての使命を担っていくことをお約束いたします。本日は誠にありがとうございます。
続いて、経済産業省製造産業局産業機械課の藤木俊光課長(当時)、文部科学省研究振興局基盤研究課の柿田恭良課長(当時)から祝辞があった。藤木氏は「全力でこの国の科学と技術を支援していく」、柿田氏は「研究開発を支える基盤を充実、強化する」と述べ、いずれも日科協に向けて大きな支援、エールがこめられた言葉であった。
また、友好団体であり合同展示会「JASIS」の共同主催者である「一般社団法人日本分析機器工業会」の副会長 栗原権右衛門氏(当時)より祝辞があり、「これからも、JASISに限らず、2つの団体は手を携えまして協力関係をより強固なものにして、いいコラボレーションをつくりあげていきたい」という熱意あるメッセージが贈られた。
式典の最後に、日科連の役員として功績のあった元役員33名の表彰式が行われた。受賞者を代表して、日科連の前会長であった入江名誉会長から、「日本科学機器団体連合会の法人化については、積年の課題であり、ようやく法人化がかなったことに、一際、感慨深いものがあり、今後とも会がますます発展することを祈念します」と挨拶があった。長きにわたり会長をつとめ、法人化に尽力してきた入江名誉会長の万感の思いがこもった言葉であった。その後、関連学会・団体から寄せられた祝電の披露、日科協の新役員の紹介、岡野忠弘副会長の閉式の辞と五行歌の朗読により式典が終了した。
第二部の記念祝宴は、京の祇園の芸妓さん、舞妓さんによる祝舞いにより華やかに始まった。祝賀会実行委員会の木崎民生委員長より開宴の挨拶と矢澤会長から御礼の挨拶があり、独立行政法人科学技術振興機構の顧問 北澤宏一先生からの祝辞のあと、日科協相談役の堀場雅夫氏による乾杯の音頭があり、懇親・交流の宴が繰り広げられた。
佐藤紀一副会長からの閉宴の挨拶をもって、約3時間にわたった式典・祝宴は盛況裡に幕を閉じた。
●新法人のもと、さまざまな事業を展開
新法人となり、「科学機器」の発行をはじめ、さまざまな事業が次々と展開されていった。
展示会委員会(佐藤紀一委員長)並びに総覧委員会(長谷川壽一委員長)主導により、2010(平成22)年から日本分析機器工業会との合同展として開催してきた「分析展・科学機器展」を2012(平成24 )年より、JASIS(Japan Analytical and ScientificInstruments Show)と名称を統一。両業界にとって、さらなる政策的な発展を目指した。
その後はJASISとして毎年行われ、2016(平成28)年には、すでに9月7 ~ 9日に幕張メッセ国際展示場で「JASIS 2016」が開催されることが決定している。
JASISとして統一されたことにより、「科学機器総覧」と「分析機器総覧」が合本され、2012(平成24)年から「科学・分析機器総覧」として1冊にまとめられた。毎年改訂され、JASISだけでなく、サイエンスエキスポや最新科学機器展でも配布されている。2013(平成25)年からはCD-ROM版も製作されている。また、掲載されている科学機器は、WEB科学機器総覧(http://www.soran.net/about/index.html)でも見ることができる。
加えて前述した「JASIS」(日科協とJAIMAによる共同主催)の他にも、技術委員会(入江一光委員長)、経済委員会(志智裕之介委員長)、国際委員会(下平克彦委員長)、広報委員会(柴田眞利委員長)による事業活動を展開している。
【主な活動】
1.技術委員会
(1)科学機器学習教室の開催
科学機器学習教室は、2007年度から年に4回開催されてきており、新人社員教育、若手営業職の科学機器についての基礎知識の習得など、従業員のスキルアップに活用されていたが、会場は東京、大阪、東海のみであった。そこで2014年度から、地方の北海道や九州などの地域でも同教室が実施できるように各協会に対し、135機種を網羅した冊子『科学機器入門』の受講者への提供や講師の派遣などの学習支援活動を展開し、延べ2,644名の会員が受講し研鑽を積んでいる。
(2)見学会・講演会の開催
見学会・講演会は、年1回開催されており、近年は「JAXA」、「福島再生可能エネルギー研究所」、地球深部探査船「ちきゅう」などの見学会やノーベル物理学賞受賞の小林誠高エネルギー加速器研究機構特別栄誉教授、中村修二カリフォルニア大サンタバーバラ校教授の講演会などを実施し、会員の技術知識の向上に努めている。
また、産業技術総合研究所や東京理科大学と連携し、「講演会及び研究者との交流会」を定期的に開催して産学官連携活動を推進している他、経産省・中小機構・JST等の支援事業やシーズ報告・新技術などの各種情報を継続的に配信し、会員の便宜に供している。
(3)業界標準EMS「ISO14001認証取得」支援の実施
(一社)産業環境管理協会と協力し、日科協版標準EMS(環境マネジメントシステム)を利用して、会員のISO14001認証取得に関する支援事業を継続的に実施している。
(4)毒物劇物取扱者資格試験受験準備講習会の開催
(公社)日本理科教育振興協会及び(一社)日本教材備品協会との共催で、同受験準備講習会を毎年実施している。
2.経済委員会
(1)「会員実態調査」、「景況に対する会員アンケート調査」の実施
「会員実態調査」が、新法人のもと2012(平成24)年11月から12月にかけて、867社を対象に行われた。矢澤英人会長は、「科学機器」2012年11月号の巻頭言において「『会員実態調査』は企業活動及び協会運営の基礎資料」と述べ、会員企業に協力をよびかけた。主な調査項目は、「会社概要」、「業種・従業員数、営業状況」、「採用・退職、定年・退職金、給与」、「休日、労働時間」、「出張旅費」、「福利厚生制度」、「情報化」、「リスク管理」、「日本科学機器協会の事業活動について」で、「リスク管理」が東日本大震災を経て加わった。
2014(平成26)年には、加えて「景況に対する会員アンケート調査」を実施。これも会員実態調査と同様、もともとは東京科学機器協会により東京地区で行われていたが、日科協の事業として全国の会員企業を対象に実態調査とは別に毎年行われることになった。
(2)見学会・講演会の開催
年1回、技術委員会と共催で前述の各見学会・講演会を開催している他、未来予測講演会などを実施し、会員の経済意識の高揚を図っている。
(3)「生産性向上設備投資促進税制」証明書の発行
2014年1月20日より産業基盤を強化するための同促進税制が施行され、生産性向上設備などの中、先端設備に係る証明書発行団体として経産省に登録されており、対象設備の要件(最新モデル、生産性向上:年平均1%以上)と合致する製品について証明書の発行を実施している(2017年3月末まで)。
3.国際委員会
(1)海外の科学機器展視察ツアーの開催
PITTCON展(米国)及びACHEMA展(独)への出展参加並びに調査研修ツアーを開催し、海外の科学機器業界関連企業と会員との情報交換及び技術交流に努めている。
(2)海外事情などに関するセミナーの開催
通商貿易に関する関係法令改正や国際規格、海外事情などに関するセミナーや講演会を適宜開催している他、ASIC(アジア科学機器業界団体会議)加盟団体並びに内外の関係機関との情報交換及び交流に努めている。
(3)JETRO貿易実務オンライン講座の提供
日本貿易振興機構(ジェトロ)と団体契約を結び、 JETRO貿易実務オンライン講座の受講料を割引価格で会員に提供している。
4.広報委員会
(1)機関誌「科学機器」の発行
全国の会員をはじめ、官公庁、関係学会、関連団体など関係機関に配布しているこの機関誌は、「N.R.K」という名称で、1948(昭和23)年に日科協(旧日科連)の前身である日本理化学機器商工会から発行。その後、日科連が結成された1960(昭和35)年に各地区協会が単位組織方式に移行したため、一般社団法人日本科学機器協会が設立された2012(平成24)年4月まで東京科学機器協会が機関誌「科学機器」の発行を受託・発行してきたが、月刊会誌として今日まで1号も休刊することなく発行を重ねてきた。
現在、全国組織である日科協の機関誌として「科学機器」を発行することによって、全国の会員企業にとって必要な情報はもちろん、各地区ごとの有益な情報まで詳細に提供できるようになったのである。
(2)日科協ホームページ(HP)の活用
日科協の事業内容・組織図、PITTCON展・ACHEMA展、技術情報・各種助成金制度や関連法規制などの情報を掲載し、会員に提供している。
「分析機器・科学機器遺産」 認定制度を開始
2012(平成24)年より、日本分析機器工業会との共同事業として、「分析機器・科学機器遺産」認定制度を導入、同制度による認定事業をスタートした。これは、日本国民の生活・経済・教育・文化に貢献した貴重な分析技術・分析機器や科学機器を文化的遺産として後世に伝えることを目的に、歴史的価値が高い科学機器、技術や機器に関連する文書、および資料類などを認定、表彰するという取り組みである。選定委員会は、二瓶 好正( 東京大学名誉教授)委員長をはじめとする産学官の有識者の方々により構成されている。
同年9月5日より開催されたJASIS2012で、一回目の「分析機器・科学機器遺産」に認定された製品の展示と認定証授与式が行われた。認定されたのは20製品であり、その中には、科学機器総覧の前身である東京理化学器械同業組合カタログ「T.R.K」第3版も含まれていた。
2013(平成25)年に実施した第二回の認定以降、一般からの応募も受けつけた。当初、この認定制度は3回にて終了の予定であったが、その重要性を鑑みて、2015(平成27)年現在も継続されている。
【選定委員会】
委員長 :二瓶 好正 氏(東京大学名誉教授)
石井 格 氏(国立科学博物館名誉研究員)
石谷 炯 氏 (神奈川科学技術アカデミー名誉顧問)
久保田 正明 氏 (産業技術総合研究所客員研究員)
古谷 圭一 氏 (東京理科大学名誉教授)
山崎 弘郎 氏 (東京大学名誉教授)
●新法人として「2012第7回高雄国際儀器展」へ参加
新法人としても、2012(平成24)年に開催されたタイ科学機器展である「Thailand Lab 2012」(旧Lab Tech)への出展参加、PITTCON調査研修ツアーやACHEMA化学工業視察ツアーを実施するなど、海外の科学機器業界との交流は変わらず行われていた。世界経済的には特にアジアの新興国の経済成長が大きなインパクトを与えており、ASICで育んできたアジアの科学機器業界との絆はより重要な意味をもつようになっていた。
中でも初の試みとなったのが、2012年7月19日~21日の3日間、台湾・高雄にて開催された「2012第7回高雄国際儀器展」への参加である。高雄国際儀器展は、高雄市経発局と高雄市儀器商業同業公會の共催で実施され、同公會より無償でブースの提供を受け、初の出展を果たした。このブースにて、日科協として初めて開催する「JASIS 2012」への勧誘活動を行った。
台北市に続く大都市である高雄市は、大工業都市であり、科学機器のメーカーのほとんどが集中している。ちなみに、台北市は高雄市とは対照的に科学機器のディーラーが集まっているという。
業界関係者の話によると、当時の台湾の科学機器のマーケットは、そのほとんどが半導体市場をはじめとする民間需要であり、官学の研究機関が購入する機器は海外製品で占めているとのことだった。また、粗悪な中国製品が流通していることに対し、懸念する声が高まっており、日本と似た状況も垣間見られた。その後、この高雄国際儀器展への参加は継続して行われるようになった。
●科学機器業界として初の「賀詞交歓会」を開催
日科協が新法人として新たなスタートを切った2012(平成24)年は、政治的・経済的に苦しい中にあったものの、世の中においても新時代を予感させる出来事が多い年であった。
例えば3月には、地上アナログ放送が終了し、全国で完全デジタル化が完了、5月に東京タワーに替わる新たな電波塔「東京スカイツリー」が完成した。また10月には、京都大学の山中伸弥教授がiPS細胞の作製に世界で初めて成功したことにより、ノーベル医学・生理学賞を受賞した。科学機器業界にとっては、この年最も明るいニュースとなった。新しい多能性幹細胞であるiPS細胞(人工多能性幹細胞)により、再生医療を中心に今後の医療が変わるとの期待が高まっていった。ちなみに、山中伸弥氏は当時の経済産業省大臣枝野幸男氏との会談のなかで「試薬や機器はできるだけ国産のものを使って研究開発したい」と述べたという。科学機器業界にとっては、非常に心強い、エールとも捉えることのできる言葉であった。12月に行われた衆議院議員総選挙により、政権が民主党から自由民主党へと移行し、それにより、自民党・公明党の自公連立政権による第2次安倍内閣が発足した。
こうした時代の流れの中で迎えた2013(平成25)年、1月11日グランドプリンスホテル新高輪(東京)において、「賀詞交歓会」が開催された。日本科学機器協会の前身団体から続く67年間の歴史を振り返っても、都内における賀詞交歓会の開催は初めてのことだった。会員企業はもちろん、官庁はじめ、学会、大学、研究機関等から多数の出席があり、253名が参加する盛大な会となった。新年の挨拶において、矢澤英人会長は“全国統一組織として活動の幅を拡げ、社会全体に貢献していく”という決意を改めて述べた。来賓を代表して、経済産業省製造産業局産業機械課課長の須藤治氏(当時)、文部科学省研究振興局基盤研究課課長の柿田恭良氏(当時)、東京理科大学学長・初代東京大学特別栄誉教授の藤嶋昭先生より祝辞があった。
経済産業省の須藤治氏は、経済政策は「震災復興・富の拡大への投資・国民の安全安心」が大きな柱になっていること、日本の富の源泉は製造業であり、そのコアとなるのは研究開発であること、試験研究が産業の強さの基盤であることなどを述べられ、いずれにおいても科学機器の役割が重要だと強調した。
文部科学省の柿田恭良氏は、日本再生に向けた緊急経済政策について、文部科学省として研究開発、イノベーションの推進という柱立ての下、先端的な研究開発、研究基盤の強化・整備・高度化、大学等における地域に開かれた研究設備の導入などを促進していくことが盛り込まれていると説明した。そして、国産の技術、国産機器の導入・普及が大切だとして、「文科省として国産機器の開発強化をあらためて施策として進めたい」と業界にとって頼もしい言葉を送られた。
藤嶋昭先生は、「当然ながら日本は科学技術で食べていかなければならないということで、その後継者をいかに作っていくか、理科離れをいかに防ぐかというのが一番大事なことではないか」と科学機器産業に携わる人々のみならず、日本の未来に向けて全ての人にかかわる課題を提起された。さらに藤嶋先生は、全国の中学、高校を対象とした「理科の出前授業」を行った経験から、「子供たちが目を輝かせて『理科が面白い』と言ってくれます。これが一番大事なことではないかと思っているのです。<中略>皆様方も、身の回りの面白いことをどんどん、いろいろなところでお話しいただいて、理科好きを育ててください」と呼びかけた。
祝辞の後は、藤嶋昭先生による乾杯の音頭で賀詞交歓となり、終始和やかな雰囲気の中、会が終了した。
●アベノミクスの一環「生産性向上設備投資促進税制」に積極的に協力
2012(平成24)年末以降、安倍内閣による、いわゆる“アベノミクス”と呼ばれる経済政策が進められていた。これは、「大胆な金融政策」「機動的な財政政策」「民間投資を喚起する成長戦略」の3本の矢を基本とし、「デフレからの脱却」と「富の拡大」を目指したものである。
「大胆な金融政策」「機動的な財政政策」の2本の矢については、早い段階に放たれていたが、残されていたのが「民間投資を喚起する成長戦略」であり、これこそが科学機器業界が期待する矢であった。
2014(平成26)年3月、いよいよ「民間投資を喚起する成長戦略」の一環として「生産性向上設備投資促進税制」が施行された(2017年3月31日まで)。これは、事業者が「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を導入する際に優遇税制を受けられるようにすることで、事業者の生産性向上を図り、日本経済の発展を図ろうとするものである。一方で、設備メーカー・ディーラーにとっては販売促進につながる税制措置でもあり、科学機器の中にもその対象となる製品が多く存在していた。
この税制措置を受けるには、A類型(先端設備)では工業会等、B類型(生産ラインやオペレーションの改善)では経済産業局の確認(証明書の発行)が必要となる。A類型の場合、設備を購入したユーザーは設備メーカー・ディーラーに証明書発行を依頼、メーカー・ディーラーは所属団体等に証明書発行を依頼し、発行された証明書はメーカー・ディーラーからユーザーに渡されるという流れである。
日科協は、この税制措置に証明書発行団体の一つとして積極的に協力、経済産業省と二人三脚で証明書発行を実施している。日科協が発行した証明書は、2014年度が508件、2015年上期が378件に及んだ。このように膨大な件数となっているのは、自身の会員企業からの依頼のみを請け負っている工業会が多い中、日科協は会員企業以外の一般企業の依頼にも対応、科学機器業界のみならず日本経済の発展に向けて広く門戸を拡げているためであった。
さらに日科協では、会員企業のメーカー、ディーラーがこの税制をユーザーへの販売促進活動に活用できるように、東京・大阪・東海地区の科学機器協会を通じて、勉強会を定期的に開催した。
●日科協として新たな活動を展開―創立70周年を迎えて
2015(平成27)年、日科協は創立70周年を迎えた。創立70周年記念事業として、11月16日、「創立70周年記念祝賀会」を実施した。本書『日本科学機器協会70年史』の発行も記念事業の一つである。2015年「科学機器」新年号の巻頭言において、矢澤会長は以下のように述べている。
日本の科学機器産業は国の科学技術研究費、企業の研究開発費、さらには先端科学技術を駆使した生産設備などによって、業績を伸ばしてきました(平成25年度の科学技術研究費の総額は18兆1,336億円、対前年度比4.7%増)。これに依存するだけでやってこられたことで海外への関心の薄い企業も多いことは考えられますが、グローバル化、産業構造の変化の中で、近い将来、科学機器産業の構造的変化も起こってくることが考えられます。<中略>この70年の間で、科学機器産業の技術的内容も大きく変化しました。また、業界も時代の流れとともに大きく進歩・発展を続けてきました。この変化が、さらなる10年、50年への確実な礎石になることを期して、70年を祝いたいと思っているところです。